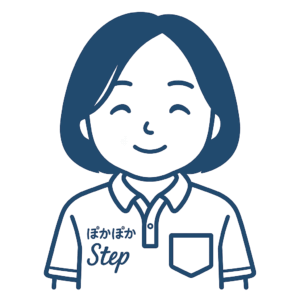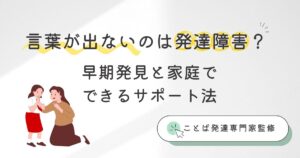子どものことばの発達は、月齢や年齢によって大きく変化します。
しかし、成長のスピードには個人差があるため、「同じ年齢なのに言葉が少ない」「発音がはっきりしない」など、保護者や先生が不安になることも少なくありません。
本記事では、年齢別のことばの発達の目安を解説し、もし、ゆっくりだった場合の相談先、療育の活用についても詳しく紹介します。
児童発達支援管理責任者としての経験から、現場での支援事例やアドバイスも交えてお伝えします。
ことばの発達には個人差がある

ことばの発達は、「この年齢になったら必ずこれができる」というものではありません。
遺伝や性格、環境、発達特性など、さまざまな要因が影響します。同じ年齢でも、早くからおしゃべりが得意な子もいれば、しばらく様子を見てから一気に話し出す子もいます。
特に初めての子育てでは、周囲の子と比べて「うちの子は遅いかも…」と不安になることも多いでしょう。しかし、単なる個性の場合も少なくありません。
「早い・遅い」だけで不安にならず、成長の過程や全体の様子を見ていくことも大切でしょう。
例えば、言葉は少なくても、ジェスチャーや表情で意思を伝えている場合は、コミュニケーション能力が発達してきていると考えられます。
一方で、言葉だけでなく指差しや視線の共有が少ない場合は、専門機関への相談を検討してみてもよいと思われます。
 児発管いずみ先生
児発管いずみ先生ことばの発達は子どもの心と体の成長とも深く関係しており、
焦らずに見守りつつ、必要な時に早めの支援へつなぎましょう
早い・遅いだけで判断しないための考え方
「同じ年齢のあの子はもうこんなに話しているのに…」と感じても、単純に早い・遅いだけで発達を気にするのではなく、理解力やコミュニケーションの方法も含めて総合的に見る必要があります。
たとえば、発語は少なくても、指差しや視線、身振りで意思を伝えている場合は、言葉以外のコミュニケーション力が育っていると思われます。
反対に、単語は多くても会話のやりとりが続かない場合や、相手の言葉の理解が難しい場合、なにかしらの支援が必要になることもあります。
保護者や先生は「今はどの力が伸びていて、どんなサポートが必要か」を把握していくと良いでしょう。
そのためには、日常の中での様子を丁寧に観察し、園や学校、必要に応じて専門機関と情報共有しながら、発達のペースに合った関わりを続けていくことが望まれます。
年齢別ことばの発達目安


1歳頃(初語が出る時期)
1歳頃は、「ママ」「ブーブー」など意味のある単語(初語)が出始める時期です。まだ発音は不明瞭ですが、特定の人や物を指して発話するようになります。
また、「バイバイ」といった簡単な言葉や動作の模倣も見られます。この時期は、ことばを話す力よりも、聞く力(理解力)が大きく伸びる時期です。
「ちょうだい」「おいで」など簡単な指示に反応したり、家族や身近な人の呼びかけに振り向く様子が出てきます。
発語がまだ少ない場合でも、指差しやアイコンタクト、ジェスチャーで意思表示できているかが重要な観察ポイントです。
これらが育っている場合は、ことばの土台が整ってきていると考えられます。一方で、名前を呼んでも反応が乏しい、指差しをほとんどしないなどの場合は、聴覚や発達特性の影響がないか早めに確認すると安心です。
保護者は「話すこと」を急がせるよりも、たくさん話しかけたり、一緒に遊びながら言葉を聞く機会を増やしてあげると良いでしょう。
1歳半〜2歳頃(二語文が出始める)
1歳半を過ぎると、語彙がぐんと増え始め、「ワンワン きた」「ママ おいで」などの二語文が出る子が増えてきます。
語彙数は30~200語以上になる時期で、「これなあに?」と質問をするなど、会話のやりとりが活発になります。発音はまだ未熟で聞き間違えやすいことも多いですが、この時期は「話すことの楽しさ」を感じ始める大切な時期です。
理解力も大きく伸び、「○○持ってきて」「赤いボールちょうだい」など2段階の指示に応じられるようになります。また、「イヤ」「もっと」など自分の気持ちを言葉で表す機会も増えてきます。
ただし、この時期も発達のペースは個人差が大きく、二語文がまだ出ていなくても、単語が増えていたり、理解力が育っていれば問題ない場合もあります。
一方で、発語や理解の伸びがゆるやかで、ジェスチャーも少ない場合は、保健センターや専門機関に相談してみることも考えていくと良いかもしれません。
家庭では、子どもの発話を繰り返して肯定的に返す「オウム返し」や、日常生活の動作を実況する「言語化」の働きかけをすると良いでしょう。
3歳頃(簡単な会話が成立する)
3歳頃になると、語彙は1,000語程度になり「今日は○○へ行った」「○○食べたよ」など、3〜4語の文章で出来事を話せるようになります。
簡単な質問にも答えられるようになり、会話のキャッチボールが成立し始めます。語彙はさらに増え、色や形、数などの概念語も出てきます。この時期は、言葉での自己表現が広がる反面、「なんで?」「どうして?」と質問攻めになることも多く、好奇心旺盛な時期でもあります。
発音はまだ未熟で「サ行」「ラ行」が不明瞭なこともありますが、家族以外の大人にもある程度意味が通じるようになります。
一方で、話はできても順序立てて説明することが難しく、内容が飛びやすいのも特徴です。日常生活の中で「何から話すと相手に伝わるか」を経験できるよう、聞き手としてゆっくり相槌を打ち、話を促してあげることが大切です。
4〜5歳頃(語彙が増え、会話がスムーズになる)
4〜5歳になると、体験や物語を順序立てて話せるようになり、「まず〜して、それから〜」と時間の経過を踏まえた表現も可能になります。
語彙は飛躍的に増加し、形容詞や副詞なども使えるようになるため、話の内容が豊かになります。発音はほぼ明瞭になり、初対面の大人でも理解できるレベルになります。
この時期は友達同士の会話やごっこ遊びを通して、言葉のやりとりのスキルが大きく伸びます。相手の発言を受けて返す、複数人で話題を共有するなど、社会的な会話も発達する時期です。
ただし、まだ抽象的な概念や複雑な説明は難しいことが多く、誤解や言い間違いもよくあります。
保護者や先生は、正しい言葉を押し付けるのではなく、自然に正しい表現に言い換えて返す「リキャスト法」が有効です。



「きのう 動物園 行く」という子どもの発言に対して
「そうなんだ、昨日動物園 に 行った んだね。何の動物がいたの?」と
会話の中で自然に正しい形に直します。
6歳頃(文法の誤りが減り、説明ができるようになる)
6歳頃になると、理由や因果関係を含めた話ができ、「〜だから〜なんだよ」と論理的に説明できるようになります。
文法の誤りも減り、複雑な文章構造を使いこなせるようになってきます。就学に必要な言語力がほぼ整い、授業や集団生活の中での理解・発表もスムーズになります。
また、この時期は相手の立場や気持ちを考えながら話す力が育ちます。物事の背景や理由を説明したり、簡単なルールや手順を他者に伝えることができるようになります。
一方で、話を端的にまとめる力はまだ発展途上で、説明が長くなったり脱線することもあります。家庭や学校では、「順番に話す」「大事なことから話す」といった会話の整理方法を練習する機会をつくると、今後の学習や人間関係にも役立つでしょう。
ことばの発達がゆっくりなのかもしれないサイン


発語が極端に少ない
同年代の子と比べて、明らかに言葉の数が少ない場合は、ことばの発達がゆっくりな可能性があります。
例えば、1歳半を過ぎても意味のある単語がほとんど出ていない、2歳を過ぎても「ママ」「ワンワン」など数えるほどしか言えない、といったケースです。
発語が少ない背景には、単なる個人差もあれば、聴覚の問題や発達特性(ASDや知的発達症など)が関係している場合もあります。
発語の量だけで判断せず、理解力やジェスチャーでの意思表示があるかを観察することも大切です。
例えば、名前を呼ぶと振り向く、指差しで欲しい物を示すなどの行動があれば、コミュニケーション能力は育っていると考えられるかもしれません。
反対に、理解や非言語コミュニケーションも乏しい場合は、早めに専門機関(保健センター、小児科、言語聴覚士など)へ相談することも一案に入れても良いかもしれません。
保護者は、無理に言葉を促そうとするよりも、子どもが興味を持つ場面で声をかけ、楽しくやりとりを増やすことを心がけましょう。
発音が不明瞭で伝わりにくい
年齢に比べて発音が著しく不明瞭な場合も、発達の遅れや音の習得に課題があるサインかもしれません。
3歳を過ぎても家族以外にはほとんど言葉が通じない、5歳を過ぎても「サ行」「ラ行」だけでなく多くの音が置き換わる、などです。
発音の不明瞭さには、口や舌の動きの発達がゆっくりである場合や口腔機能、聴覚の問題などが関わることがあります。また、ASDや構音障害など、言語発達に関連する特性の一つとして見られることもあります。
重要なのは、発音が多少未熟でも意欲的に話しているか、会話が成立しているかを観察することです。
本人が「通じない」経験を繰り返すと、自信を失い、話すこと自体を控えてしまうことがあります。
園や学校と協力して環境調整を行い、必要に応じて言語聴覚士による構音支援を取り入れると良いでしょう。
家庭では、正しい発音を何度も練習させるよりも、大人が自然に正しい形で言い返して聞かせる方法(リキャスト)が有効です。
会話のやりとりが続かない
相手の問いかけに対して短く答えるだけで、その後の会話が続かない場合は、個人の性格もありますが、ことばの発達やコミュニケーション力の面で支援が必要な可能性もあります。
例えば、「今日何したの?」と聞いても「遊んだ」で終わってしまい、詳しく話す、相手に質問を返すといったやりとりが見られないケースです。
原因としては、語彙の不足や文の組み立ての難しさ、質問の意図を理解することが難しいなどが考えられます。
また、ASD(自閉スペクトラム症)の特性である相互的コミュニケーションの難しさや、注意が続きにくいADHDの傾向が影響していることも考えられるでしょう。
会話のキャッチボールは、単に話すだけでなく「聞く→理解する→考える→返す」という複数のスキルを同時に使うため、かなり高度になってきます。
支援の際は、短い文章で質問する、写真や絵カードを使って話題を可視化するなど、やりとりをしやすい環境を整えてあげると良いでしょう。
指差しやジェスチャーも少ない
ことばの発達は、言葉そのものだけでなく、非言語的なコミュニケーションの発達とも密接に関わっています。
特に指差しは「共同注意」と呼ばれ、相手と関心を共有する重要な発達のステップです。1歳前後で、興味のあるものを「見て!」と指差ししたり、欲しいものを指さして伝える姿が見られてきます。
しかし、この指差しや手振りがほとんど見られない場合は、ことばの習得に必要な土台がまだ育っていない可能性や、ASDや言語発達の緩やかさなどの特性が関係していることもあります。
また、ジェスチャーが少ないと発語が増える前の意思疎通が難しく、言語発達のペースが緩やかになることがあります。
支援としては、保護者や支援者が積極的に指差しや手振りを使って話しかけ、「同じものを見て・同じ反応をする」経験を繰り返すことが有効と思われます。



視線や動作を共有する遊び(「いないいないばあ」や指差し絵本)も、
ことばの芽を育てる関わり方です。
ことばの発達が遅れていると感じたら


家庭でできること(読み聞かせ・声かけの工夫など)
ことばの発達に不安を感じたら、まずは日常生活の中でできる関わりを増やすことが大切です。
絵本の読み聞かせは、語彙を増やすだけでなく、親子のやりとりを豊かにします。読むときは抑揚をつけたり、絵を指さしながら「これはなにかな?」と問いかけると、子どもの反応を引き出しやすくなります。
また、「○○持ってきて」「赤い車どこ?」など、日常の動作や物に関する指示を出すことで、理解力と語彙を同時に育てられます。
発語が少なくても、指差しやジェスチャーで答えたら「そうだね、赤い車だね」と言葉にして返すことがポイントです。
一方で、無理に話させようとすると逆効果になることもあります。子どもが興味を持っているタイミングや、感情が動いた瞬間を逃さず声をかけるよう意識しましょう。
「できた!」「すごいね!」など肯定的なフィードバックは、話す意欲を高めます。
園や学校の先生との情報共有
家庭だけでなく、園や学校での様子を知ることも重要です。集団生活の中での行動や反応は家庭とは異なるため、先生から得られる情報は発達の全体像を把握する手がかりになります。
例えば、家では発語が少なくても、園では友だちとよく話している場合もあれば、その逆もあります。
活動中の集中力や指示の理解度、友だちとの関わり方など、ことばの発達に関連する行動を先生が観察していることも多いです。



情報共有の際は、「家ではこういう様子がある」と具体的に伝えると、
園側も観察の視点を持ちやすくなります。
また、園と家庭で支援方法を揃えることで、子どもは混乱せずに同じルールや声かけに慣れることができます。
保護者と先生がチームとして関わることで、より効果的なサポートが出来るでしょう。
早めに相談すべき専門機関(市区町村の相談窓口、言語聴覚士、児童発達支援など)
ことばの発達に不安がある場合は、「もう少し様子を見よう」と先延ばしにするより、早めに相談することも大切です。
市区町村の保健センターや子育て支援センターでは、発達相談や言語相談を無料で受けられることがあります。
医療機関では、小児科や耳鼻科で聴覚や発達の状態を確認でき、必要に応じて言語聴覚士(ST)による評価につなげてもらえます。
また、児童発達支援事業所では、遊びや活動を通じてことばやコミュニケーションを育てる個別支援を行っているところもあります。
早期に専門家とつながることで、家庭での関わり方のヒントや、子どもに合ったトレーニング方法を知ることができるでしょう。小さな変化にも気づきやすくなり、ことばの伸びをサポートしやすくなると思われます。
療育や専門的支援の活用


児童発達支援・放課後等デイサービスでのことばの支援
児童発達支援や放課後等デイサービスは、発達に心配のある子どもが日常生活や学習に必要な力を身につけるための福祉サービスです。
ことばの発達支援では、遊びや活動を通して語彙の拡大、発音練習、会話のやりとり、気持ちや要求の表出などを行います。
施設では、児童発達支援管理責任者が子どもの発達状況を把握し、個別支援計画を作成します。この計画に基づき、保育士や指導員が一人ひとりのペースや興味に合わせた支援を行っていきます。
たとえば、絵カードを使って物の名前を覚える、自分の要求を伝える、順序立てて話す練習をするなどの支援を行っていきます。
また、園や学校との連携も行われるため、家庭・施設・学校の3つの場で一貫したサポート体制を作ることができるのも大きなメリットです。
言語聴覚士(ST)による訓練内容
言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist:ST)は、ことばやコミュニケーションの発達を専門に支援する国家資格者です。
構音(発音)や語彙、文法、会話スキルなど、子どもの課題に合わせて支援を行います。
構音支援では、舌や唇の動きを意識的に練習し、正しい音の出し方の課題に取り組みます。また、語彙の拡大や文章の組み立ての練習では、絵カードやゲームを使いながら、子どもが楽しみながらいろいろなスキルを身につけられるよう工夫されています。
STは医療機関や療育施設に所属していることが多く、発達の評価や家庭での関わり方の指導も行います。専門的な視点からの助言は、保護者にとっても大きな安心材料となります。
親子で取り組むコミュニケーション練習
療育や専門家による支援と並行して、家庭でのコミュニケーション練習を継続することが、ことばの発達を後押しします。
親子での会話は日常のどんな場面でも取り入れられます。例えば料理をしながら材料の名前を言う、散歩中に見つけたものを言葉で共有するなど、自然な会話の中で語彙を増やせます。
子どもが話した内容は最後まで聞き、正しい言い方にさりげなく言い換えて返す(リキャスト法)ことで、無理なく正しい表現を学べます。
また、写真や絵を見ながら「何してる?」と質問し、動作や状況を説明させることも表現力アップにつながります。
親子での会話は「練習」ではなく「楽しいやりとり」として行うことが大切です。



ポジティブな体験の積み重ねが、
子どもの「もっと話したい」という意欲を育てます。
まとめ|「年齢の目安」を知ることで早期支援につなげよう
ことばの発達には大きな個人差があります。年齢ごとの目安はあくまで参考であり、「早い・遅い」だけで発達段階を決めるものではありません。
しかし、その目安を知っておくことで、発達の流れを捉えやすくなり、必要な支援のタイミングを見逃しにくくなります。
もし発達の遅れや気になるサインが見られても、早期に家庭・園・学校・専門機関が連携して関わることで、子どものことばやコミュニケーションの力は大きく伸びます。
特に幼児期は脳に柔軟性があり、新しい経験や刺激を吸収しやすい時期です。
保護者や先生は、日常の中での小さな成長を見逃さず、肯定的な関わりを続けることが大切です。
そして「様子を見る」だけでなく、不安を感じたら早めに相談する姿勢が、子どもの未来の可能性を広げます。
年齢の目安は、焦るためではなく、支援を前向きに始めるための道しるべです。
安心して学び、話し、伝え合える環境づくりが、子どもの自己肯定感を高め、自信と成長を育てます。
私がいるぽかぽかステップこ・と・ばでは、ことば特化型の児童発達支援・放課後等デイサービスとして、ことばに難しさを抱えるお子様に支援を行っております。
体験・見学は下記のフォームからお申し込みください!