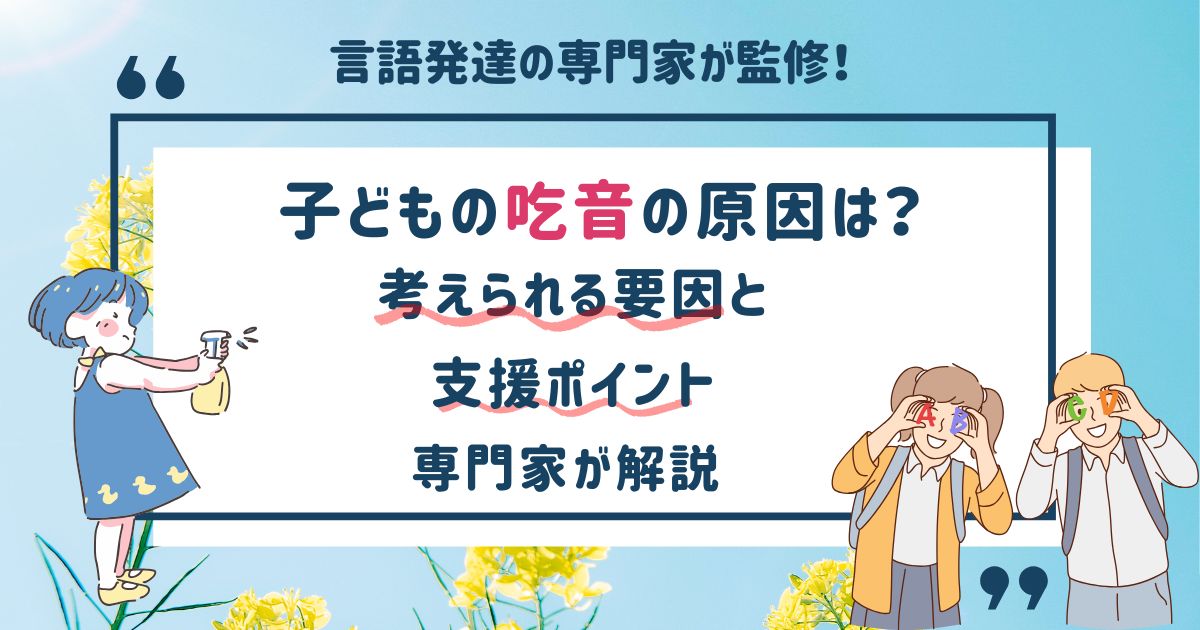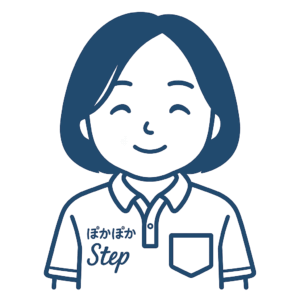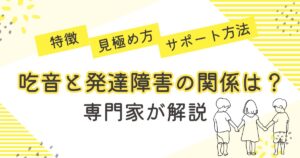「言葉が詰まってなかなか出てこない」「同じ音を何度も繰り返してしまう」——
吃音は幼児期から見られることが多く、成長とともに改善する子もいれば、大人になっても続くケースもあります。
保護者や先生にとっては、「原因は何なのか」「治るのか」「どんな支援をすればよいのか」といった疑問や不安がつきものです。
本記事では、吃音の原因と考えられている要素、年齢や症状ごとの改善の見込み、そして家庭や学校でできる支援方法について、児童発達支援管理責任者の視点から詳しく解説します。
さらに、言語聴覚士による専門的な訓練や、実際の改善事例、受診の目安も紹介。吃音の理解を深めることで、子どもの自己肯定感を守りながら将来の選択肢を広げる一歩につながれば幸いです。
吃音とは?基礎知識と症状の特徴

吃音(きつおん)とは、話し言葉の流れがスムーズに続かず、特定の音や語を繰り返したり、引き伸ばしたり、言葉が詰まって出てこない状態を指します。
幼児期に見られることが多く、2〜5歳頃に発症することが一般的です。
吃音は本人の努力不足やしつけの問題ではなく、脳の言語処理や運動制御に関わる仕組みが一時的または持続的に影響を受けている状態です。
ここでは、主な症状や経過、種類の違いについて整理します。
吃音の主な症状(繰り返し・引き伸ばし・詰まり)
吃音の症状は大きく3つに分類されます。
- 繰り返し(連発)
「か、か、か、かえる」のように、語や、音の一部を繰り返します。最も多く見られるタイプで、聞き手にもわかりやすい特徴です。 - 引き伸ばし(伸発)
「かーーえる」のように、音を不自然に長く伸ばします。本人は「言葉を出そう」としているのにスムーズに切り替わらない状態です。 - 詰まり(難発)
言葉の出だしで声が出ず、しばらく沈黙してしまうもの。「……かえる」のように間が空くため、本人が強い緊張や焦りを感じやすい特徴があります。
これらの症状は日によって軽くなったり強くなったりし、話す場面や相手によっても変動します。
発症時期と経過の一般的な傾向
吃音は多くの場合、2〜5歳頃のことばの爆発期に現れます。
この時期は語彙が急速に増え、文法を使った会話が始まるため、脳の言語処理負荷が高くなるタイミングです。
経過としては、以下のようなパターンが見られます。
- 一時的に強くなる時期がある(疲れや緊張、環境の変化などで悪化)
- 成長とともに自然に改善する場合も多い(およそ6〜8割は自然消失)
- 思春期以降も続くケースもある(発症から長く経過しても症状が固定する場合)
早期から適切な環境調整や支援を行うことで、改善の可能性が高まります。
一時的な吃音と慢性的な吃音の違い
吃音には大きく分けて発達性吃音と獲得性吃音がありますが、子どもに多いのは発達性吃音です。
- 一時的な吃音(発達性・一過性)
ことばの発達スピードと脳の調整機能が一時的にアンバランスになることで起こります。多くは半年〜1年以内に改善します。 - 慢性的な吃音(持続性)
症状が長期間続き、本人が強く意識することで悪化する傾向があります。心理的要因や発達特性、家庭・学校環境など複合的な影響を受けやすく、適切な支援が必要です。
一時的なのか慢性的なのかは見た目だけでは判断できないため、半年以上症状が続く場合や悪化傾向がある場合は早めの相談が推奨されます。
子どもの吃音の主な原因
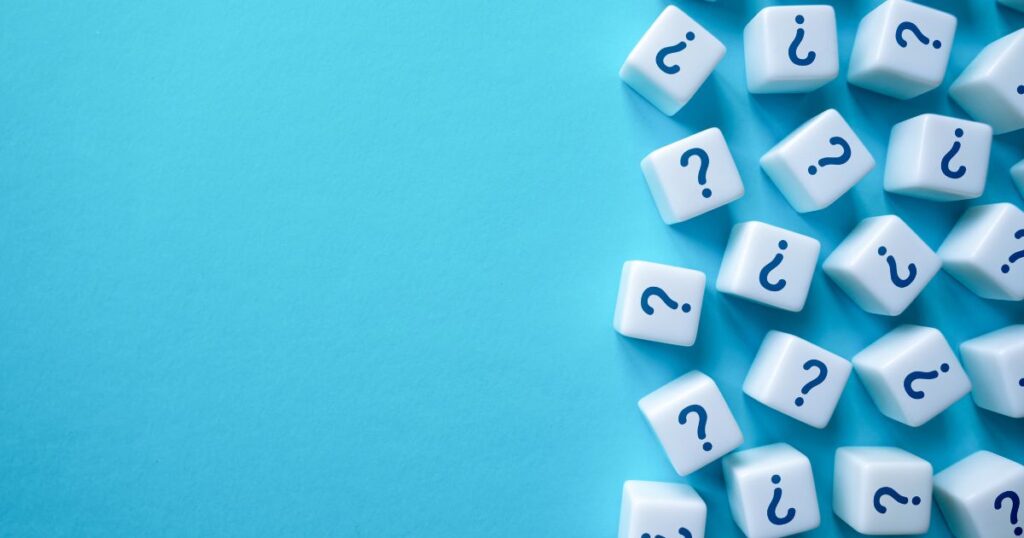
吃音の原因は一つではなく、複数の要因が重なって生じることが多いと考えられています。
現在の研究でも「これが唯一の原因」という明確な答えは出ていませんが、脳の発達や言語処理の特性、心理的要因、環境的要因が関係していることがわかっています。
ここでは代表的な原因を整理します。
発達の過程で起こる一時的なことばのつまずき
幼児期のことばの発達は、語彙や文法の急速な習得が特徴です。
この時期は、脳の言語処理能力と発話の運動機能がまだ十分に連動していないため、「話したい内容は頭に浮かんでいるのに、口が追いつかない」状態が生じやすくなります。
これにより、言葉がスムーズに出ず、繰り返しや詰まりといった一時的な吃音が現れることがあります。
多くの場合、成長に伴って自然に改善します。
遺伝や脳の機能によるもの
吃音は家族内での発症が比較的多いことから、遺伝的な要素が関与していると考えられています。
また、脳の言語処理に関わる領域(左半球のブローカ野や運動野)や、それらをつなぐ神経ネットワークの発達や働き方に特徴があることも報告されています。
これらは本人の努力や育て方とは無関係です。
心理的要因や環境的ストレス
吃音の発症や悪化には、心理的な緊張やプレッシャーが影響する場合があります。例えば、
- 引っ越しや進級などの生活環境の変化
- 新しい人間関係への不安
- 「急いで話して」と促される経験
などが、ことばを発する場面への不安感を高め、症状を強めることがあります。
また、周囲が吃音を指摘したり真似をしたりすると、本人が話すこと自体に恐怖心を持つことがあり、悪循環につながります。
発達障害(ASD・ADHD・LDなど)との関連性
ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)、LD(学習障害)といった発達障害の特性を持つ子どもの中には、吃音を併せ持つケースがあります。
これは、情報処理のスピードや注意の切り替え、社会的場面での緊張の高さなどが、発話の流暢さに影響するためです。
この場合、吃音だけでなく発達特性全体に配慮した支援が必要です。
原因に応じた関わり方と支援の工夫

吃音は原因によって関わり方や支援の方法が変わりますが、どの場合も共通して大切なのは、子どもが安心して話せる環境をつくることです。
ここでは主な原因ごとの具体的な支援の工夫を紹介します。
安心できる環境を整える
吃音のある子どもは、人前や急かされる場面で症状が強くなる傾向があります。
そのため、まずはことばを安心して発することができる場をつくることが第一歩です。
- 話を最後まで遮らずに聞く
- 笑ったり真似をしたりしない
- 話の内容に注目し、話し方は評価しない
こうした関わりが、子どもの自己肯定感を保つうえで大切です。
ことばを急かさず、最後まで聞く姿勢を持つ
吃音がある子どもは「早く言わなきゃ」と焦るほど症状が悪化しやすくなります。
保護者や先生は、子どもの話すペースを尊重することを心がけましょう。
- 言葉を途中で補わない
- 「落ち着いて」「ゆっくり話して」という指示よりも、うなずきや視線で促す
- 他の子と比較する発言を避ける
これにより、話すことへの不安感を軽減できます。
プレッシャーや緊張を減らすための工夫
人前での発表や初対面の人との会話など、緊張が高まりやすい場面では、事前に準備や練習をすることが有効です。
- 発表やスピーチの練習を少人数で行う
- 話す順番や内容をあらかじめ決めておく
- 話さないといけない場面の直前には深呼吸やリラックス法を取り入れる
こうした準備が「話せるかどうか」の不安を和らげます。
専門的な訓練・療育の活用
吃音が長引いたり日常生活に影響を及ぼしている場合は、専門家による支援が効果的です。
- 言語聴覚士(ST)による発話練習
- 児童発達支援事業所でのコミュニケーション療育
- 学校の特別支援コーディネーターによる配慮調整
早期に専門的な介入を行うことで、改善や軽減が期待できます。
吃音の原因が疑われるときに相談できる機関
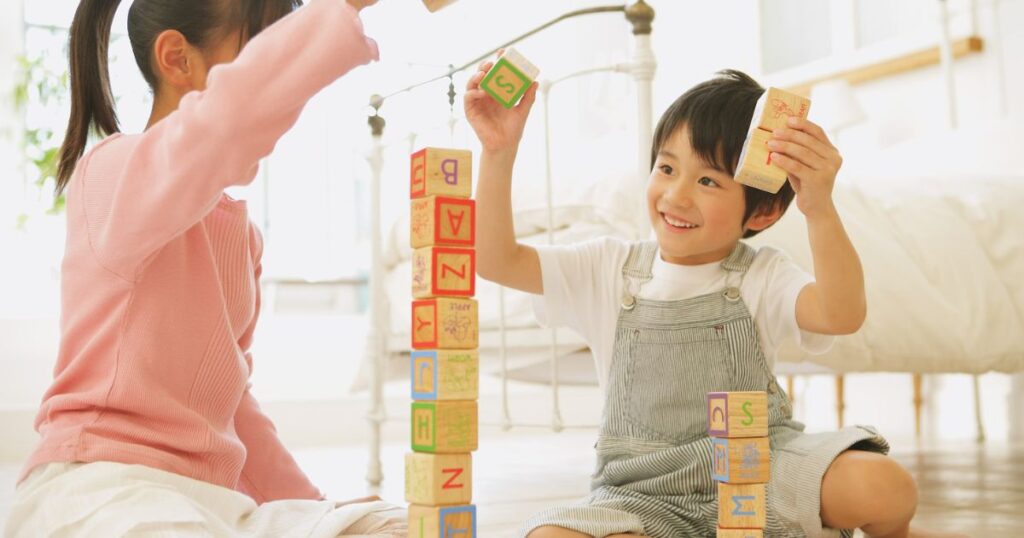
吃音は、原因や経過によって必要な支援が異なります。
ご家庭や学校だけで判断するのではなく、専門機関への相談が安心です。
ここでは、吃音が疑われる場合に頼れる相談先と、それぞれの特徴をご紹介します。
言語聴覚士(ST)がいる医療機関
吃音の評価や支援を専門に行うのが言語聴覚士(Speech Therapist:ST)です。
小児科や耳鼻咽喉科、リハビリ科などに所属しており、以下のようなサポートを受けられます。
- 吃音の種類や程度の評価
- 発話の流暢さを高める練習
- 家庭での関わり方の指導
受診する際は、事前に「言語聴覚士が在籍しているか」を確認しましょう。
発達支援センターや児童発達支援事業所
地域の発達支援センターや児童発達支援事業所では、吃音を含む言語発達の遅れや特性に合わせた療育を行っています。
保育士や言語聴覚士、臨床心理士などがチームで支援を行うことが多く、遊びや集団活動を通してコミュニケーション力も育てます。
筆者が在籍しているのも、「ぽかぽかステップこ・と・ば」という、ことばの発達特化型の児童発達支援事業所・放課後等デイサービスです。
教育委員会・学校の特別支援コーディネーター
就学前や就学後であれば、教育委員会の就学相談窓口や学校内の特別支援コーディネーターに相談できます。
学校での発表や友達との会話など、学習場面での配慮方法を一緒に考えてくれます。
- 発表の順番や内容の事前共有
- 話しやすい場面設定
- 話し方よりも内容を評価する指導
地域の子育て支援窓口
1歳半健診や3歳児健診で言葉の相談ができる保健センターは、吃音の初期相談にも対応しています。
必要に応じて、医療機関や発達支援機関を紹介してもらえます。
また、子育て支援センターでは、保護者同士の情報交換や専門職の相談日なども活用できます。
まとめ│原因を知り、安心できる環境づくりから始めよう
吃音は、発達の過程や脳の働き、心理的要因、さらには発達障害との関連など、さまざまな要因が複合的に関わって生じます。
原因を一つに絞ることは難しいですが、大切なのは「話し方よりも話す内容を大切にする姿勢」と「安心できる環境づくり」です。
早期に専門機関へ相談し、家庭や学校での関わり方を整えることで、改善や軽減につながることもあります。
焦らず、子どものペースを尊重しながら、支えていきましょう。
まずはお気軽にご相談ください
家庭や学校での工夫はもちろん大切ですが、言語聴覚士や児童発達支援の専門家と連携することで、より効果的な支援が可能になります。
ぽかぽかステップこ・と・ばでは、吃音や言葉の発達に課題を抱えるお子さまに合わせた個別支援計画を立て、自己肯定感を守りながら成長をサポートしています。
「うちの子は受診した方がいいの?」「学校にどんな配慮をお願いすればいいの?」と迷われた際は、ぜひ一度ご相談ください。
専門スタッフが丁寧にお話を伺い、お子さまに合った支援の形をご提案いたします。