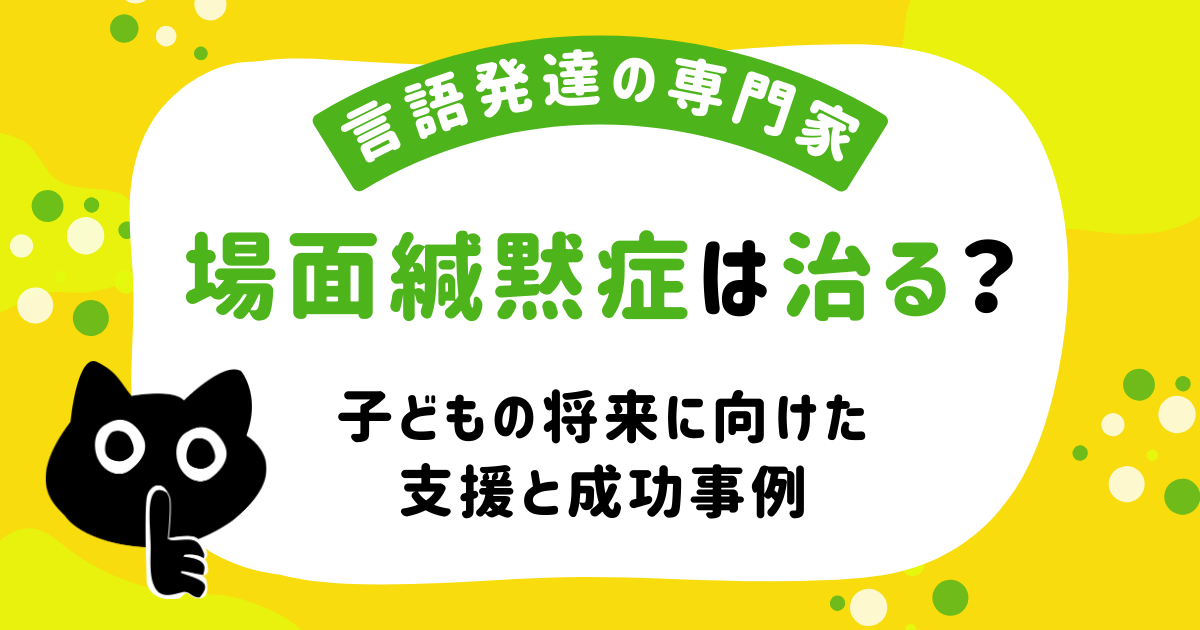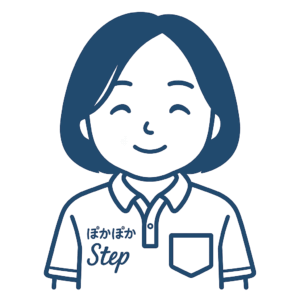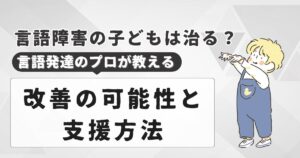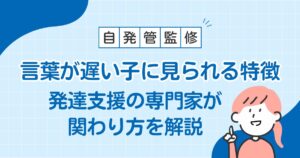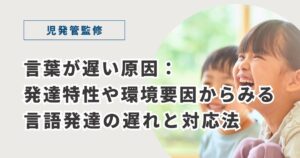子どもが家庭では話せるのに、学校や園では言葉が出なくなる──
これは単なる「恥ずかしがり」や「性格の問題」ではなく、場面緘黙症(ばめんかんもくしょう)という症状かもしれません。
場面緘黙症は、不安や緊張から特定の場面で話せなくなる不安障害の一種で、適切な理解と支援が必要です。
本記事では、場面緘黙症の子どもに見られる症状や原因、家庭や学校での支援方法、医療機関で受けられる治療、そして改善の見通しについて、ことば特化型療育施設の児童発達支援管理責任者の視点から詳しく解説します。
将来への不安を軽減し、安心して子どもを育てるためのヒントを一緒に見つけていきましょう。
場面緘黙症とは?症状と特徴
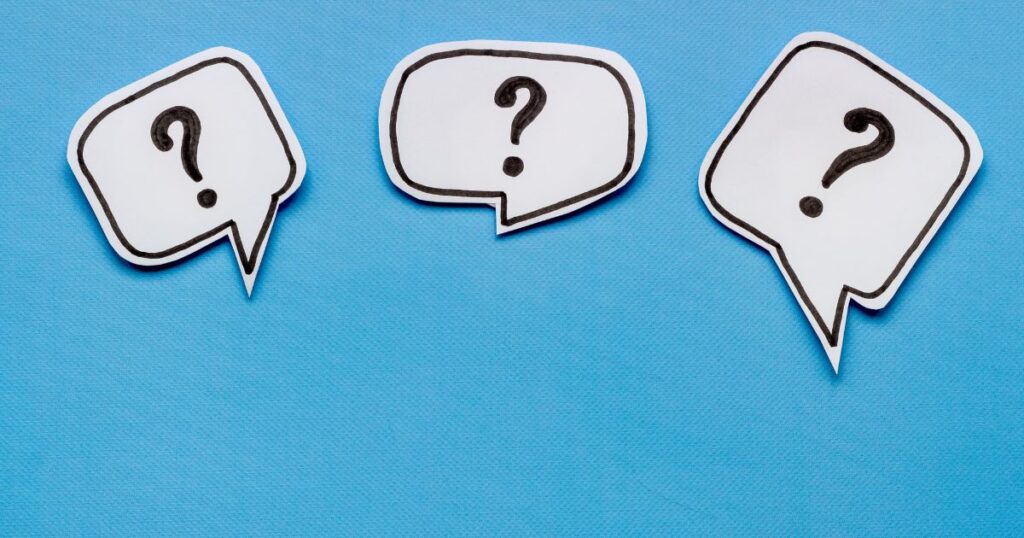
場面緘黙症の基本的な定義と症状
場面緘黙症(ばめんかんもくしょう)とは、家庭など安心できる場面では普通に会話できる一方で、学校や園など特定の場面では極端に話せなくなる状態を指します。
本人は「話したくない」のではなく、「話したいのに声が出ない」という強い不安に直面していることが多く、不安症の一種として分類されています。
周囲からは「無口」「恥ずかしがり屋」と誤解されやすいのですが、実際には本人に強い心理的負担がかかっています。
症状の現れ方は、まったく声が出ない場合もあれば、限られた人にだけ小声で話す場合もあります。
書く・ジェスチャーで意思表示するケースも多く、本人の努力不足ではなく心理的な困難が背景にあることを理解することが大切です。
発達障害や内気・恥ずかしがりとの違い
場面緘黙症は発達障害や単なる「性格」と混同されやすい特徴があります。
ASD(自閉スペクトラム症)の場合は、対人関係全般において会話や相互交流が難しくなるのに対し、場面緘黙症の子どもは家庭や安心できる相手との会話では問題なく話すことができます。
また、単なる「内気」や「人見知り」であれば、環境に慣れるにつれて少しずつ話せるようになりますが、場面緘黙症の場合は時間が経っても症状が続くことが多いです。
つまり、本人の意思や性格だけでなく、不安や恐怖心が強く関与している点が特徴です。
この違いを理解せず「育て方の問題」「甘え」と捉えると、本人や家族が孤立してしまうため、正しい理解と支援が欠かせません。
診断基準と年齢別に出やすい特徴
場面緘黙症は、DSM-5(精神障害の診断・統計マニュアル)で「選択性緘黙」として診断基準が定められています。
その内容は「特定の社会的状況において一貫して話すことができない」「そのために学業や社会生活に支障が出ている」「持続期間が1か月以上」「言語能力や会話スキルの不足では説明できない」などです。
年齢別にみると、幼児期(3〜5歳)では入園後に急に話さなくなるケースが多く、小学校低学年では授業中の発言や友達との会話が困難になることが目立ちます。
思春期以降まで症状が続くと、不登校や対人不安など二次的な問題につながることもあるため、早期の理解と支援が重要です。
場面緘黙症の原因と背景要因
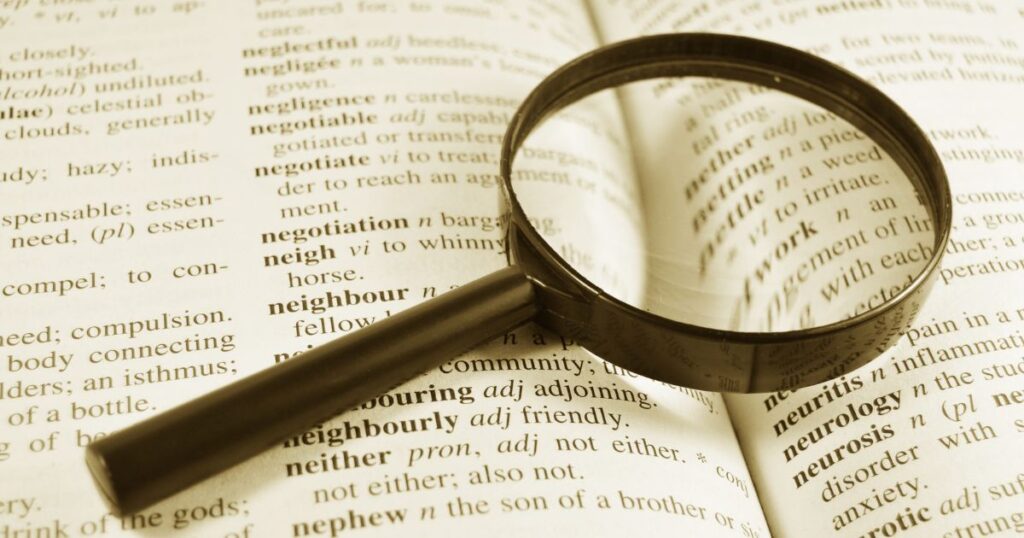
不安症や対人恐怖との関連
場面緘黙症は、不安症の一種と考えられています。
特に「社交不安障害」との関連が強く、他者からどう見られるかに強い恐怖を感じることで、声が出なくなるケースが多いです。
例えば「間違えたら笑われるのではないか」「注目されると緊張する」といった不安が積み重なり、話そうとしても体が固まってしまうのです。
このため、本人は「話したくない」のではなく「話したいのに声が出ない」という苦しさを抱えています。
見た目には無口に見えるため、周囲から理解されにくいですが、実際は強い不安や恐怖反応が根底にあることを理解することが大切です。
家庭環境・学校環境など環境要因の影響
場面緘黙症の発症や持続には、環境的な要因も大きく関わります。
例えば、家庭内での過度な叱責や緊張感の強い雰囲気、学校でのプレッシャーやいじめ・不登校の経験などが症状を悪化させることがあります。
また、園や学校で「みんなの前で発表することが当たり前」といった文化が強調されると、さらに不安が高まることも少なくありません。
一方で、安心できる環境や「無理に話さなくても良い」と受け止めてもらえる経験は、改善に向けた大きな一歩になります。
つまり環境は悪化要因にも支援要因にもなり得るため、家庭・学校双方で子どもが安心して過ごせる土台をつくることが必要です。
性格・気質的な要因の影響
場面緘黙症の子どもには、不安を感じやすい気質や内向的な性格傾向がみられることが多いとされています。
遺伝的に不安が強く出やすいタイプの子どもや、感覚過敏を持つ子どもは、環境からの刺激に対して敏感に反応しやすいため、緘黙が現れるリスクが高いといわれています。
ただし、性格そのものが原因ではなく、気質と環境が相互に作用することで症状が出やすくなる点に注意が必要です。
例えば、繊細な気質の子どもが安心できるサポート環境にいれば症状は出にくく、逆にプレッシャーの強い環境では緊張が高まり話せなくなります。
このため、本人の気質を理解しつつ、安心できる場を広げていくことが支援の基本になります。
家庭でできる支援と接し方

「無理に話させない」安心できる環境づくり
家庭でまず大切なのは「話させることを目標にしない」ことです。
場面緘黙症の子どもは「話したいのに話せない」という強い葛藤を抱えており、「早く話しなさい」「どうして話せないの?」と急かされると、さらに不安が高まり症状が悪化することがあります。
家庭では「話さなくても受け入れてもらえる」安心感を積み重ねることが支援の第一歩です。
例えば、身振りや絵、文字で伝えた時に「ありがとう、伝えてくれて嬉しいよ」と肯定的に受け止めることが、子どもにとって大きな安心につながります。
安全な居場所があることで、少しずつ外でも安心を広げていける土台ができます。
声かけや励まし方の工夫
家庭での声かけは「話すことを直接求めない」工夫が必要です。
「今日は話せた?」と成果を聞くよりも、「学校でがんばったね」「一緒に過ごせて楽しいよ」と気持ちを認める関わりが有効です。
また、子どもが少しでも声を出せた時には「よくできたね」と大きく褒めるのではなく、自然に受け止めることが大切です。
過剰な注目はかえってプレッシャーになるため、あくまでも“さりげなく肯定する”姿勢を意識しましょう。
家庭内で歌やごっこ遊びなど、言葉を強制せず自然に声が出る活動を取り入れるのも効果的です。楽しみながら声を使う機会を積み重ねることで、少しずつ自信を取り戻していけます。
きょうだいや友人を巻き込んだ自然なコミュニケーション支援
場面緘黙症の子どもにとって、信頼できる相手との関わりが支援の大きな助けになります。
家庭では、きょうだいや仲の良い友人と遊ぶ時間を意識的に増やし、安心できる人間関係の中で自然に声を出す練習ができるようにすると良いでしょう。
例えば、きょうだいと一緒に遊んでいる中で保護者が加わり、会話の橋渡し役になることで、子どもが少しずつ発言しやすくなることもあります。
また、友人と一緒に遊びながらゲームや共同作業に取り組むことで、会話が目的ではなく自然な流れの中で言葉が引き出されることもあります。
大切なのは「話せたかどうか」よりも「安心できる時間を共有できたか」を重視する姿勢です。
学校・園での具体的な支援方法
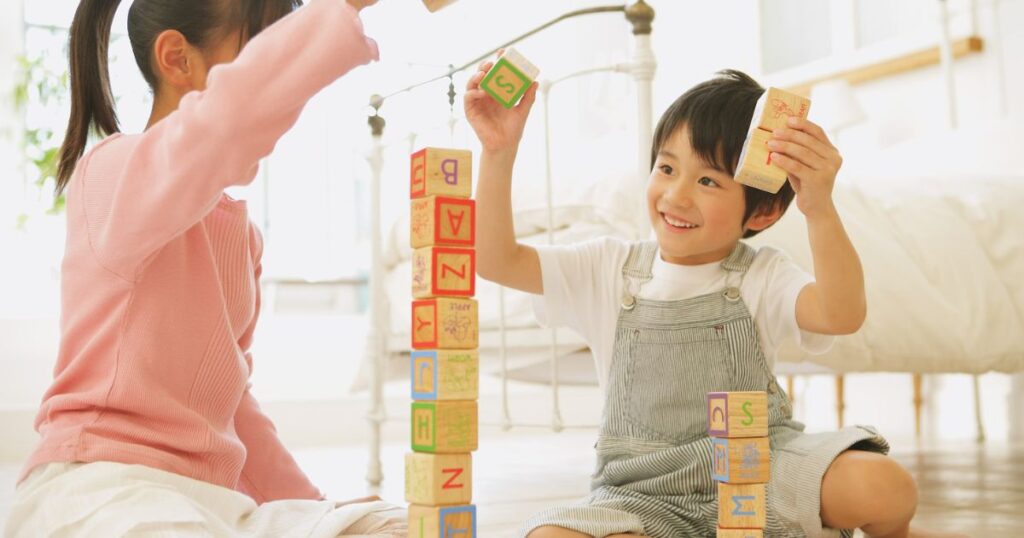
教師ができる配慮(発表を強制しない、代替手段を用意する)
学校や園で大切なのは「みんなと同じように話させること」を目標にしないことです。
場面緘黙症の子どもは、声を出せないことを自分でも理解しており、無理に発表をさせられると強い不安や恐怖からますます声が出にくくなります。
そのため、授業中の発言や自己紹介の場面では、プリントに書く・カードを掲げる・ICTを使って入力するなど、言葉以外の方法で表現できる代替手段を用意することが有効です。
また、提出物やテストで回答をしっかり書ける力があっても「声を出せない」ことだけで評価が下がらないよう、教師の理解が欠かせません。子どもの努力や学習を正しく評価しつつ、安心できる経験を積ませていくことが大切です。
同級生への説明や理解を促す
周囲の子どもたちの理解も、場面緘黙症の支援において重要な要素です。
「どうして話さないの?」と友達から聞かれることは本人にとって大きなプレッシャーになるため、
教師が事前に
「〇〇さんは緊張すると声が出にくくなるんだよ」
「話さなくても一緒にいられるだけで嬉しいよね」
と自然に伝えることで、誤解や孤立を防ぐことができます。
また、友達が代弁してくれたり、共同作業の中で役割を分担したりすることで、本人が安心して参加できる雰囲気が広がります。
クラス全体が「話すことだけが評価ではない」という認識を持てると、場面緘黙症の子どもも安心して学校生活を送れるようになります。
合理的配慮としてできる支援の例
学校には「合理的配慮」が求められています。場面緘黙症の子どもに対しては、発表や音読の免除、筆談や録音による代替手段、少人数での発表機会の設定などが効果的な支援策です。
また、担任の先生だけでなく、養護教諭やスクールカウンセラー、特別支援教育コーディネーターと連携し、子どもに合った配慮を計画的に行うことが大切です。
さらに、保護者との情報共有も欠かせません。家庭でできていることや、安心して話せる相手について共有することで、学校でも支援がスムーズに進みます。
「声を出すこと」だけをゴールにせず、安心して学びに参加できる環境を整えることが、場面緘黙症の子どもにとっての最大の支援となります。
医療機関・専門機関での治療と支援

小児科・心療内科・精神科での診断と治療
場面緘黙症が疑われる場合、まずは小児科や児童精神科を受診して診断を受けることが大切です。
診断では、DSM-5(精神障害の診断基準)に基づき、症状の持続期間や学業・生活への影響を確認します。
医師は子どもの発達歴や家族からの聞き取りを行い、必要に応じて心理検査を組み合わせて総合的に判断します。
治療の基本は薬ではなく、環境調整や心理的支援です。
ただし、不安が強く日常生活に大きく支障が出ている場合には、抗不安薬や抗うつ薬が併用されることもあります。
重要なのは「無理に話させる」のではなく、子どもの安心感を基盤に少しずつステップを踏んで支援することです。
発達支援センターや療育機関の利用
場面緘黙症の子どもは、発達支援センターや児童発達支援事業所でサポートを受けられることがあります。
これらの機関では、言葉の練習だけでなく、集団活動の中で安心できる関わりを経験しながら、少しずつ社会性を育む支援が行われます。
また、親への支援も重視されており、家庭での声かけ方法や学校との連携の仕方について助言を受けられる点が大きなメリットです。
自治体によっては療育手帳や医療費助成、自立支援医療制度が活用できる場合もあるため、専門機関と相談しながら適切な制度を利用することが勧められます。
家庭と学校だけで抱え込まず、地域の支援資源をうまく活用することが改善への近道になります。
言語聴覚士・臨床心理士による具体的な支援内容
言語聴覚士(ST)や臨床心理士は、場面緘黙症の支援に重要な役割を担います。
言語聴覚士は、ことばの発達状況を確認し、話しやすい場面を少しずつ広げていく練習を支援します。
また、絵カードやゲームを通じて「自然に声を出す体験」を積み重ねる工夫も行います。
臨床心理士は、カウンセリングや遊戯療法を通して不安を和らげる支援を行い、必要に応じて認知行動療法(CBT)などを取り入れながら、不安の軽減と自己肯定感の向上を目指します。
これらの専門家による支援は、家庭や学校でのサポートと連携することでより効果が高まります。保護者自身が相談できる機会にもなるため、安心して長期的に支援を続けられる体制づくりが可能になります。
改善の見通しと成功事例

どのくらいの期間で改善する?
場面緘黙症の改善には時間がかかることが多く、数か月で話せるようになるケースもあれば、小学校から中学・高校まで長期的に続くケースもあります。
改善のスピードは子どもの性格や不安の強さ、周囲の環境によって大きく左右されます。
ただし共通して言えるのは「早期に支援を始めるほど改善しやすい」という点です。
特に幼児期や小学校低学年の段階で家庭や学校が、理解し無理に話させるのではなく安心感を積み重ねていくことで、少しずつ声を出す機会を広げていけます。
短期間での「完治」を求めるのではなく、長期的に子どもが安心して成長できる環境づくりを続けることが大切です。
早期療育・支援による改善の可能性
場面緘黙症は「必ず一生続くもの」ではなく、適切な支援を受けることで改善が見込めます。
特に言語聴覚士や臨床心理士による専門的なサポート、学校での合理的配慮、家庭での安心感の積み重ねが相乗効果を生みます。
例えば、幼稚園で声が出なかった子どもが、少人数のグループで遊びながら少しずつ発語できるようになり、小学校では友達に限定して話せるようになる、という段階的な改善がよく見られます。
また、保護者が「話せないことを責めない」姿勢を持ち続けることで、子どもが自信を取り戻し、社会の中で声を出す練習を安心して積めるようになります。支援が早期に始まるほど改善の可能性は高まります。
成功事例や体験談から学ぶポイント
実際に改善した子どもの事例を見ると、共通して「安心できる環境」と「周囲の理解」が大きな鍵になっています。
例えば、小学校低学年まで授業中に一言も声が出なかった子が、担任の先生の配慮で「プリントに書く→小声で先生に伝える→友達に短い言葉で伝える」と段階を踏む中で、中学に入る頃にはクラスで発表できるようになったケースがあります。
また、保護者会で場面緘黙症について説明が行われ、クラス全体が「話さなくてもいいんだ」と理解した結果、子どもが安心して少しずつ声を出せるようになった例もあります。
保護者・教師が抱えやすい悩みと向き合い方

「甘え」「育て方のせい」ではないことを理解する
場面緘黙症の子どもを育てる保護者が最も悩みやすいのは、「自分の育て方が悪かったのでは」「子どもの甘えなのでは」という罪悪感です。
しかし、場面緘黙症は環境要因や性格だけでは説明できず、不安障害の一種として医学的に位置づけられています。
つまり、親の責任やしつけの問題ではありません。大切なのは「声を出さないこと」そのものを責めない姿勢です。
保護者が安心して受け止める姿勢を持つことで、子どもは少しずつ安心感を得て、話す力を広げていけます。
まずは親自身が正しい理解を持つことが、子どもへの最大の支援につながります。
家庭と学校の連携の工夫
家庭と学校で支援の方向性が食い違うと、子どもは混乱し、不安が強まることがあります。
例えば、家庭では「無理に話させない」対応をしていても、学校で「勇気を出して発表してみよう」と指導されると、子どもは板挟みになってしまいます。
そのため、家庭と学校の間で情報を共有し、支援方針を一致させることが重要です。
保護者が学校に子どもの状況を丁寧に伝え、担任やスクールカウンセラーと連携して「安心できる代替手段」を導入することが効果的です。
連携が取れていると、子どもは「どこにいても安心できる」と感じられるようになり、改善につながります。
同じ悩みを抱える家庭・支援団体とのつながり
保護者や教師は「どう支援していいかわからない」という孤独感を抱えやすいものです。
そのようなときには、場面緘黙症に関する支援団体や親の会、発達支援センターでの相談が大きな助けになります。
同じ悩みを抱える家庭の体験談を聞くことで、「うちだけではない」と安心できたり、実際に役立つ工夫を学べたりします。
また、教師にとっても、専門家や他校の実践事例を知ることは支援の幅を広げるきっかけになります。
保護者と学校が孤立して抱え込むのではなく、専門機関やコミュニティとつながることが、子どもの未来を支える大きな力となります。
将来への不安と二次障害の予防
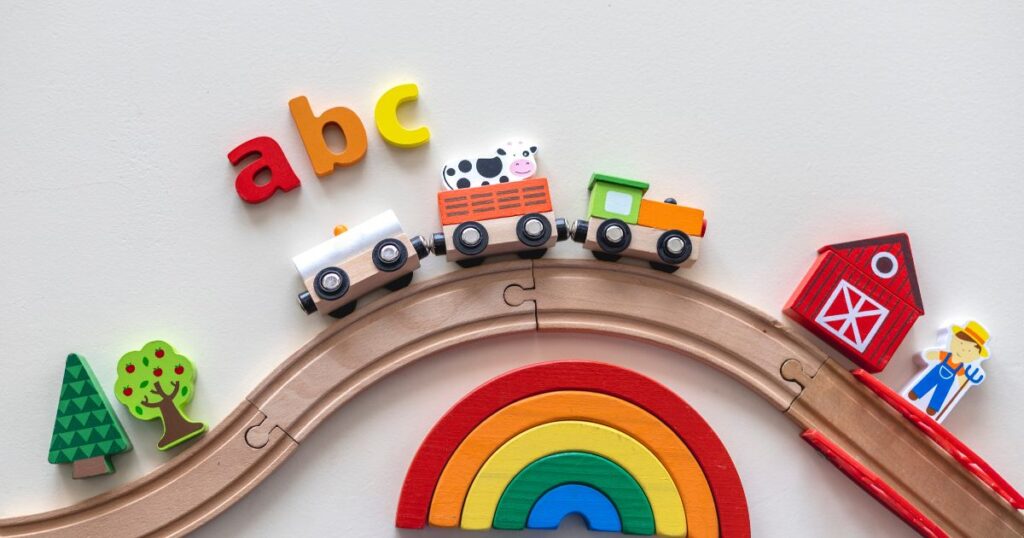
友人関係・学習への影響
場面緘黙症の子どもは、声が出せないために友人関係を築きにくく、学習面でも発表や音読が困難になります。
こうした困難は「勉強ができない子」「友だちが少ない子」と誤解されやすく、本人の自尊感情を下げてしまう要因になります。
実際には知的能力に問題がない場合が多いため、適切な代替手段を整えれば学習を十分に進めることが可能です。
友人関係についても、話さなくても一緒に遊べる活動や役割を担う場を用意することで、信頼関係を築くことができます。
将来の不安を軽減するためには、学習・友人関係の両面で「声を出す以外の方法」を保障し、安心して活動できる環境を整えることが不可欠です。
不登校・うつ・不安障害のリスクと対処
場面緘黙症を理解されずに「話さないこと」を否定され続けると、子どもは強いストレスを抱え、不登校やうつ、不安障害といった二次障害に発展することがあります。
特に思春期は自己意識が高まり、同級生との違いを強く感じるため、孤立感が一層深まる傾向があります。
こうしたリスクを防ぐためには、学校での合理的配慮や専門機関の支援を早期に取り入れることが重要です。
また、保護者が「話せなくても大丈夫」という安心感を伝えることが、子どもを二次障害から守る大きな力になります。
予防の観点では「話せるようにする」こと以上に「安心して生活できる環境づくり」が重要です。
社会的理解を広げる取り組みと支援の必要性
場面緘黙症はまだ社会的認知度が高くなく、「恥ずかしがり屋」「性格の問題」と誤解されやすい症状です。
このため、家庭や学校だけでなく、地域や社会全体で理解を広げることが必要です。
教育現場では教職員研修での周知、保護者会での情報共有が有効ですし、自治体やNPOが行う啓発活動も子どもや保護者の孤立感を減らす大きな助けになります。
また、同じ悩みを持つ家庭がつながるコミュニティがあることで、「一人ではない」と安心できます。
社会的理解が広がることで、子どもが自分らしく成長できる環境が整い、進学や就職といった将来の選択肢も広がっていきます。
まとめ│場面緘黙症の子どもを安心して育てるために
場面緘黙症は「恥ずかしがり」や「性格の問題」ではなく、不安障害の一種として捉えられる症状です。
家庭では無理に話させようとせず、安心できる環境を整えることが第一歩となります。
改善のペースは子どもによって異なりますが、早期に理解と支援を始めることで少しずつ声を出せる場が広がり、将来の選択肢も増えていきます。
大切なのは「話せるかどうか」だけで子どもを評価しないこと。安心できる環境の中で、子どもが自分らしく成長できるように周囲が伴走していくことが、改善への一番の近道です。
お子さまの「話せない」が続いていて心配…そんなときは一人で抱え込まず、専門家にご相談ください。
ぽかぽかステップこ・と・ばでは、児童発達支援管理責任者が在籍し、お子さまの特性に合わせた個別支援を行っています。
家庭や学校と連携しながら「安心して過ごせる環境づくり」と「少しずつ声を出せる経験づくり」をサポートいたします。
まずはお気軽に無料相談・施設見学にお越しください。
保護者の方のお悩みや不安をじっくり伺いながら、お子さまに合った支援方法をご提案いたします。