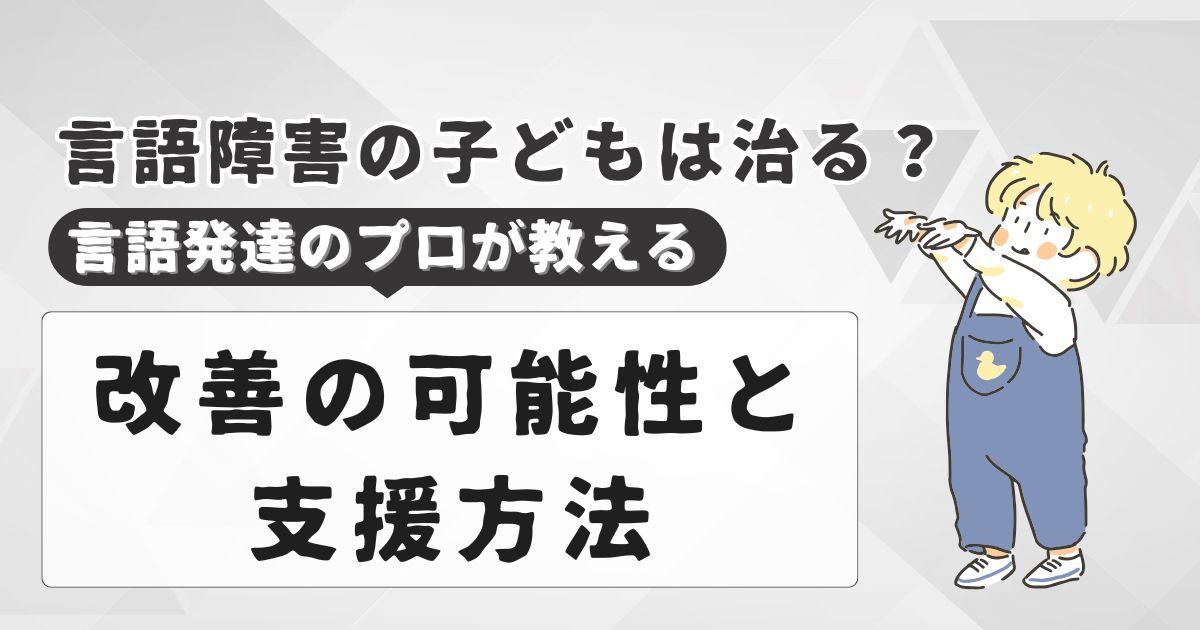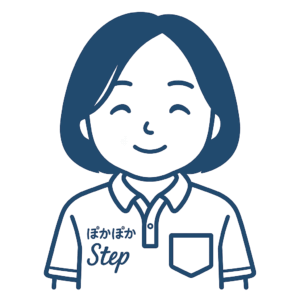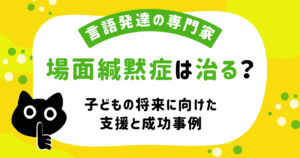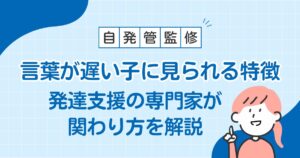「ことばがはっきりしない」「言いたいことがうまく出てこない」——
子どもの言語障害に気づいたとき、多くの保護者がまず抱くのは「治るのだろうか」という不安です。
言語障害には発音や流暢さ、言語理解などさまざまなタイプがあり、原因や年齢によって改善の見込みも異なります。
しかし、適切な時期に正しい方法で支援を受ければ、改善するケースは少なくありません。
本記事では、児童発達支援管理責任者としてことば特化型支援を行う立場から、言語障害の種類、改善事例、専門機関や家庭での関わり方までを詳しく解説します。
保護者が安心して一歩を踏み出せるよう、現場で培った実践的な情報をお届けします。
言語障害とは?種類と特徴
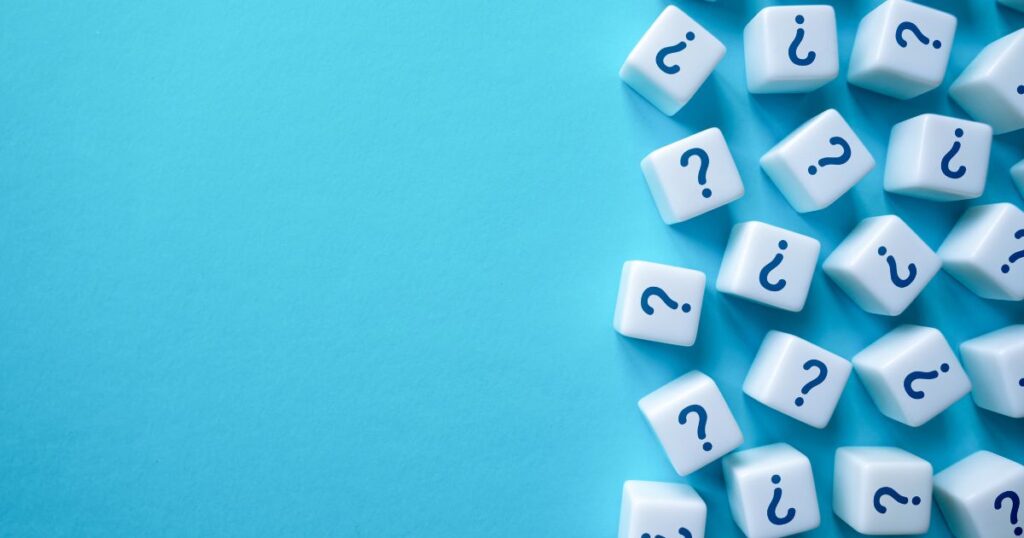
子どもの言語障害とは、発音や話す流れ、言葉の理解や表現に困難がある状態を指します。
原因は一つではなく、脳の発達や聴覚の状態、発達障害など多様です。見た目ではわかりにくいため「様子を見ましょう」と言われがちですが、適切な評価と早期の支援が改善の鍵となります。
ここでは主な種類と特徴を解説します。
発音に関する障害(構音障害など)
構音障害は、特定の音が正しく発音できない状態です。
たとえば「さ行」が「た行」に置き換わる、「ら行」が言いづらいなどが典型的です。
原因は口や舌の動かし方の習慣、歯並び、口蓋裂などの器質的要因、または聴覚障害による音の聞き分けの困難などがあります。
支援では、言語聴覚士の直接支援や監修のもとで、口の動かし方や息の使い方の練習をすることが効果的です。
また、日常生活で「正しい音を耳にする機会」を増やすことも重要で、保護者の話し方や読み聞かせの工夫が改善を後押しします。
流暢さに関する障害(吃音など)
吃音は、言葉を話すリズムや流れに繰り返し・引き延ばし・詰まりが生じる障がいです。
「き、き、きょう」「あーーのね」「……ぼくが」など、音や語の出だしで引っかかることがあります。
幼児期に一時的に現れる場合もありますが、長く続くと本人が話すことに不安を感じ、会話を避けるようになるケースもあります。
しかし早期に支援を受けることで、吃音の症状は軽減することもあります。
支援では、話す速さを落とす、言い換えや間の取り方を工夫するなど、本人が話しやすい環境づくりと心理的に安心できる環境を作っていきます。
言語理解・表出に関する障害(SLI・失語症など)
特異的言語発達障害(SLI)は、知的発達や聴覚に問題がないにもかかわらず、言葉の理解や表現が遅れる状態です。
語彙が増えにくい、文法的に間違った文を作りやすい、質問に適切に答えられないといった特徴があります。
小児失語症は、脳損傷や脳炎などの後天的要因によって、すでに獲得した言語能力が低下する状態です。
どちらも専門的な評価が必要で、支援では語彙拡大や会話練習だけでなく、理解を助ける絵やジェスチャー、PECSなど多様な手段を使います。
発達障害や聴覚障害との関連性
言語障害は単独で起こる場合もありますが、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD、LD(学習障害)などの発達障害と併発することも少なくありません。
たとえばASDでは、発音はできても会話のやり取りや文脈理解が難しいケースがあります。
また、軽度〜中度の聴覚障害では、聞き取りづらさから音の学習が不十分になり、発音や語彙に影響します。
発達や聴覚の状態を総合的に評価し、必要に応じて医療機関・療育機関・学校が連携して支援することが望まれます。
言語障害は治る?改善の可能性と限界

言語障害の回復は「年齢」「原因」「支援の開始時期」に大きく左右されます。
完全に症状が消えるケースもあれば、一定の配慮や工夫を続けながら生活するケースもあります。
「治る」というよりも、生活や学習に支障のないレベルまで改善させることを目指すのが現実的です。
年齢別の改善の目安(幼児期・学齢期・思春期)
幼児期(3〜5歳)に始まった構音障害や軽度の吃音は、早期に支援を受けることで改善する可能性があります。脳の柔軟性が高いため、新しい発音パターンや会話の方法を習得しやすい時期です。
学齢期(6〜12歳)では、習慣化した話し方や誤った発音を修正するには時間がかかりますが、学校生活に合わせた支援で改善する可能性があるかもしれません。
思春期以降は完全な修正が難しい場合もありますが、言い換えや会話の組み立て方の工夫で、周囲とのコミュニケーションを円滑にすることも、できるようになる可能性があります。
症状の種類ごとの回復の見込み
- 構音障害
-
原因が習慣や舌の使い方などであれば改善率は高い。
器質的要因の場合は手術や補助具との併用が必要なことも。 - 吃音
-
一時的な吃音は自然に消失することも多いが、慢性的な場合は「完全になくす」よりも「話しやすい話し方を身につける」方向で支援する。
- SLIや失語症
-
時間をかけて語彙や表現力を伸ばすことで生活面の困難を減らせるが、学習支援や環境調整が併行して必要になることも多い。
早期支援と脳の可塑性
脳は特に幼児期に柔軟性が高く、新しい言語パターンを学びやすい状態にあります。
早期に適切な刺激や練習を受けることで、発音や言語理解の改善は大きく促進されます。
逆に、習慣的な誤りが定着してしまうと修正に時間がかかる傾向があります。
「完全に治す」よりも「生活に困らないレベル」を目指す考え方
言語障害は、必ずしもゼロにすることがゴールではありません。
学校や職場で円滑に意思を伝えられ、本人が自信を持って話せることが大切です。
支援では「発音を直す」だけでなく、コミュニケーション全体の質を高めることを目標にします。
改善事例と実際の支援事例

言語障害の改善には個人差がありますが、適切な支援と周囲の理解があれば大きな変化が見られることも少なくありません。
ここでは、年齢や開始時期の異なる事例を4つご紹介します。
幼児期から支援を受けたケース
4歳で「さ行」が「た行」に置き換わる構音障害があり、保育園からの勧めで言語聴覚士の訓練を開始。
週1回の通所と家庭での遊びを取り入れた口の動きの練習を続けたところ、半年後には多くの音が正しく発音できるようになりました。
 児発管いずみ先生
児発管いずみ先生園生活でも友達との会話が増え、発表会で大きな声でセリフを言えるまでに成長しました。
小学校入学後に支援を始めたケース
小学2年生の男の子。文章を話すときに言葉が詰まり、クラスでからかわれることもありました。
吃音の症状を軽減するため、学校の通級指導と専門機関での支援を併用。
話す速さを意識する練習や、言い出しやすい言葉への言い換えを取り入れた結果、1年後には発表や音読もスムーズにできる場面が増え、自信を取り戻しました。
思春期から訓練を始めたケース
中学1年生で軽度のSLIと診断された女の子。
語彙の少なさや会話の組み立てに苦手さがありましたが、得意なアニメやイラストを題材に文章作りを行う個別支援を開始。
興味のあるテーマで言葉を使う練習を続けたことで、表現力が伸び、友人との会話も広がりました。
本人の自己肯定感を守りながら改善できた事例
小学5年生の男の子。
発音の誤りが残っていましたが、本人は話すこと自体が好きでした。
保護者と相談し、あえて誤りを矯正するだけでなく、スピーチや劇など得意な場面で活躍できる機会を増やす方針に。
発音練習と並行して「話す喜び」を育てた結果、周囲からの評価も上がり、自信を持って話す習慣が定着しました。
言語障害の主な支援・治療方法


言語障害の支援は、原因や症状、年齢によってアプローチが異なります。
専門機関での支援と、家庭や学校での関わりを組み合わせることで、改善のスピードや効果が高まります。
言語聴覚士による専門支援(構音練習・語彙拡大・吃音支援)
言語聴覚士(ST)は、発音、語彙、会話の流れなど、言葉に関する専門的な評価と支援を行います。
- 構音練習
-
舌や唇の動きを鏡や模型で確認しながら、正しい音の出し方を繰り返しの練習を行う。
- 語彙拡大
-
絵カードや実物、遊びや会話の中で覚えた新しい単語を生活やコミュニケーションに生かしていく。
- 吃音支援
-
話す速さのコントロール、呼吸の整え方、言い換えスキルの習得など。
個別のプランを立てるため、子どもの特性や興味に合わせた方法で行われます。
家庭でできる言葉のトレーニング(絵カード・読み聞かせ・会話の工夫)
家庭では「楽しく続けられる」環境づくりがポイントです。
- 絵カードで名前当てやしりとり遊び
- 読み聞かせで語彙や文の構造を自然に習得
- 会話の中で「正しい音や言い回しをさりげなく繰り返す」(リキャスト法)
叱ったり矯正しすぎたりすると話す意欲が下がるため、正しい形をモデルとして示すことが大切です。
ICT機器やアプリの活用
最近では、発音練習用アプリや読み上げ機能付き教材、音声認識を利用したゲームなど、ICTを活用した学習が広がっています。
- 音声波形や口の動きを視覚化してフィードバック
- 読み聞かせや発音練習を自宅で繰り返す
- 聴覚障害を伴う場合は補聴器やFMシステムとの併用も可能
家庭でも使いやすいものが多く、通所支援と併用することで学習時間を増やせます。
遊びや生活の中で自然に促す方法
日常生活の中で、料理や買い物、外遊びなどを言葉の学びの機会にします。
- 料理中に食材の名前や動作を言葉にする
- 公園で見たものを帰宅後に絵に描き、説明してもらう
- ゲーム感覚で物探しやしりとりをする
自然なやり取りの中で練習することで、子どももストレスなく取り組めます。
受診・相談のタイミングと判断基準


言語障害は「様子を見ましょう」と言われることもありますが、放置すると発音や会話の習慣が定着し、改善までに時間がかかることがあります。
特に、本人の生活や学習に影響が出ている場合は、早めの相談が安心です。
健診で指摘された場合
1歳半健診や3歳児健診で「発語が少ない」「発音が不明瞭」などの指摘を受けたら、早期に専門機関へ相談することをおすすめします。
健診は発達の節目を確認する重要な機会であり、ここでの指摘は見逃さないことが大切です。
発語や発音の遅れが半年以上続く場合
同年代の子どもと比べて、単語の数や会話のやり取りが明らかに少なく、その状態が半年以上変わらない場合は要注意です。
構音障害や発達性言語障害などが背景にある可能性もあります。
言葉以外の発達にも遅れが見られる場合
視線が合いにくい、指差しやジェスチャーが少ない、遊びが限られているなど、言語以外の発達にも気になる点がある場合は、発達障害や聴覚障害などとの関連も考えられます。
医療機関と発達支援機関の両方で評価を受けると安心です。
園や学校から指摘があった場合
保育園や幼稚園、学校の先生は、多くの子どもと比較しながら発達の違いを見ています。
第三者から「話が聞き取りにくい」「会話が続きにくい」と指摘されたら、客観的なサインとして受け止め、受診や相談を検討しましょう。
支援機関・サービスの選び方
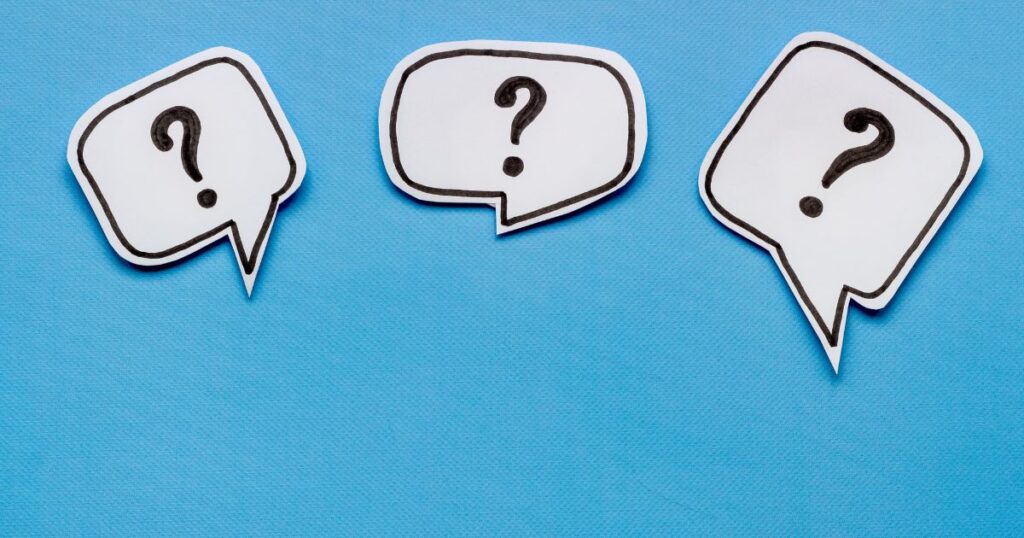
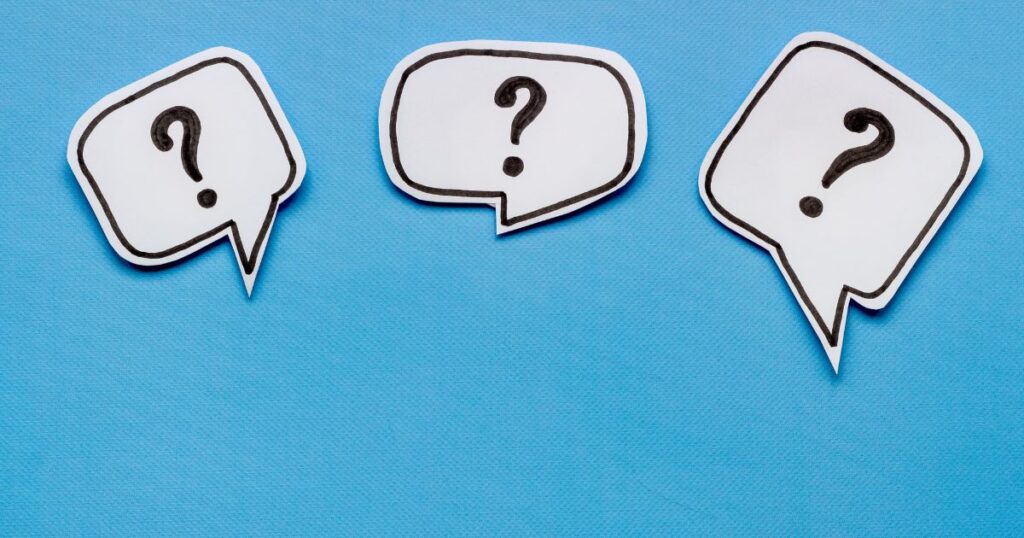
言語障害の支援は、症状や年齢、生活環境によって適した機関が異なります。
複数のサービスを組み合わせることで、家庭や学校と連携した切れ目のないサポートが可能になります。
医療機関(耳鼻科・小児科・リハビリ科)
耳鼻科や小児科では、発音や言葉の遅れの背景に聴覚や器質的な問題がないかを確認します。
必要に応じて、病院のリハビリ科で言語聴覚士による専門的支援を受けられる場合もあります。
医療保険が適用されるため、費用面の負担を抑えられるのも利点です。
療育施設・発達支援サービス
児童発達支援や発達支援センターでは、日常生活や遊びを通じて言葉やコミュニケーションの力を育てます。
個別支援計画に沿って、集団活動と個別支援を組み合わせることが多く、社会性や自己表現力の向上にもつながります。



私がいるぽかぽかステップこ・と・ばも、お子様の特性や性格に
合わせて個別支援計画を立てながら、ことばの発達をサポートしています。
放課後等デイサービス・ことば特化型教室
学齢期の子どもには、放課後等デイサービスやことば特化型の教室が選択肢になります。
学校生活で困っている場面(授業発表、友達との会話など)を具体的に想定しながら支援してくれるため、学習面や対人関係にも効果が広がります。
学校や園で受けられる支援(通級指導・特別支援学級)
公立の小中学校や一部の幼稚園には、言語障害や発達障害に対応した通級指導教室があります。
週に数時間、個別または少人数で専門的な支援が受けられます。
特別支援学級では学習内容を調整しながら、言語面を含む総合的な支援が可能です。
家庭・学校での関わり方


言語障害のある子どもは、発音や会話のしづらさから自信をなくしやすくなります。
家庭と学校が同じ方向を向いて支援することで、言葉の改善だけでなく、安心して話せる環境が整います。
自己肯定感を育む声かけ
間違いを指摘するよりも、「伝えてくれてありがとう」「よく頑張ったね」といった肯定的な言葉を優先しましょう。
うまく言えなかった時も、正しい言い方を繰り返す(リキャスト)ことで自然に学べます。
「できたこと」に注目することで、話す意欲を守れます。



たとえば、
「今日 ご飯に 食べたよ」を、
「そうだね、ご飯を食べたね!おいしかったね」と、
間違いを指摘せずさり気なく正しい言葉遣いになおします。
きょうだいや友人への説明する
家庭や学校で、きょうだいや友人に子どもの特性を簡単に説明することで、からかいや誤解を防げます。
「ゆっくり話すと聞きやすいよ」「話し終わるまで待ってね」といった具体的なサポートの方法も共有すると効果的です。
無理のない課題設定と成功体験の積み重ね
発音や会話の課題は、達成可能な小さなステップに分けます。
例えば、「今日は『さ行』の言葉を3つ言ってみよう」のように具体的で短時間でできる目標を設定します。
成功体験を重ねることで自信と意欲が高まります。
二次障害(不登校・対人不安)の予防
話すことに苦手意識が強いと、学校や友だちとの関わりを避けるようになることがあります。
早めに支援につなぎ、困っている場面を減らすことが二次障害の予防につながります。
学校と家庭が情報を共有し、授業での発表方法や評価方法を柔軟に調整することも有効です。
費用・期間・通い方の目安


言語障害の支援には時間も費用もかかりますが、公的制度を活用することで経済的負担を大きく減らすことができます。
ここでは主な制度と費用感、通所の頻度や方法の目安をまとめます。
医療保険・自立支援医療制度の活用
病院やクリニックで言語聴覚士の支援を受ける場合、多くは医療保険の対象になります。
さらに、長期的な通院が必要な場合は自立支援医療制度(精神通院医療)を利用すれば、医療費の自己負担が原則1割に軽減されます。
申請は市区町村の福祉課や保健センターで行い、医師の診断書が必要です。
制度を使うことで、数年単位の訓練でも継続しやすくなります。



詳しくは日野市のホームページをご確認ください!
療育・発達支援にかかる費用相場
児童発達支援や放課後等デイサービスは「障害児通所支援」として公費負担があり、世帯所得に応じて利用者負担上限額が設定されています。
別途、教材費やおやつ代などの実費が発生する場合がありますが、額は数百〜数千円程度に収まるケースがほとんどです。
通所頻度と期間の目安
改善に必要な期間は症状や開始年齢によって異なりますが、週1〜3回の通所と家庭での練習を並行するケースが一般的です。
幼児期に開始すれば半年〜1年で改善がみられることもありますが、学校生活での定着までを見据えると2〜3年かけて支援する例もあります。
まとめ│言語障害は早期支援で未来が変わる――家庭・学校・専門機関の連携が鍵
言語障害は、原因や症状によって改善のスピードやゴールは異なります。
しかし、幼児期からの早期支援や、本人に合った方法での継続的なサポートによって、日常生活や学習に支障のないレベルまで改善する可能性もあると思われます。
大切なのは、「治す」だけにとらわれず、本人が自信を持って話し、気持ちや要求の表出ができ、周囲とつながれる環境をつくることです。
そのためには、家庭・学校・専門機関が情報を共有し、同じ方向を向いて支えることが欠かせません。
「様子を見よう」と先延ばしにせず、気になるサインがあれば早めに相談し、一歩を踏み出すことが将来の進学や就労、そして子どもの自己肯定感を高めることにつながります。
ことばの発達に不安を感じたら、まずはご相談ください
言語障害は「早く気づき、早く支援につなぐこと」が改善の第一歩です。
ぽかぽかステップこ・と・ばでは、児童発達支援管理責任者・保育士が一人ひとりの特性に合わせて個別支援計画を立て、言葉の訓練や家庭でできる関わり方のアドバイスを行っています。
✅ 無料相談・体験支援も受付中
✅ 医療・学校と連携した総合的なサポート
✅ 保護者の方へのフィードバックと家庭での実践サポート
「もしかして…」と少しでも不安を感じたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お子さまの「話したい!」という気持ちを、一緒に育てていきましょう。