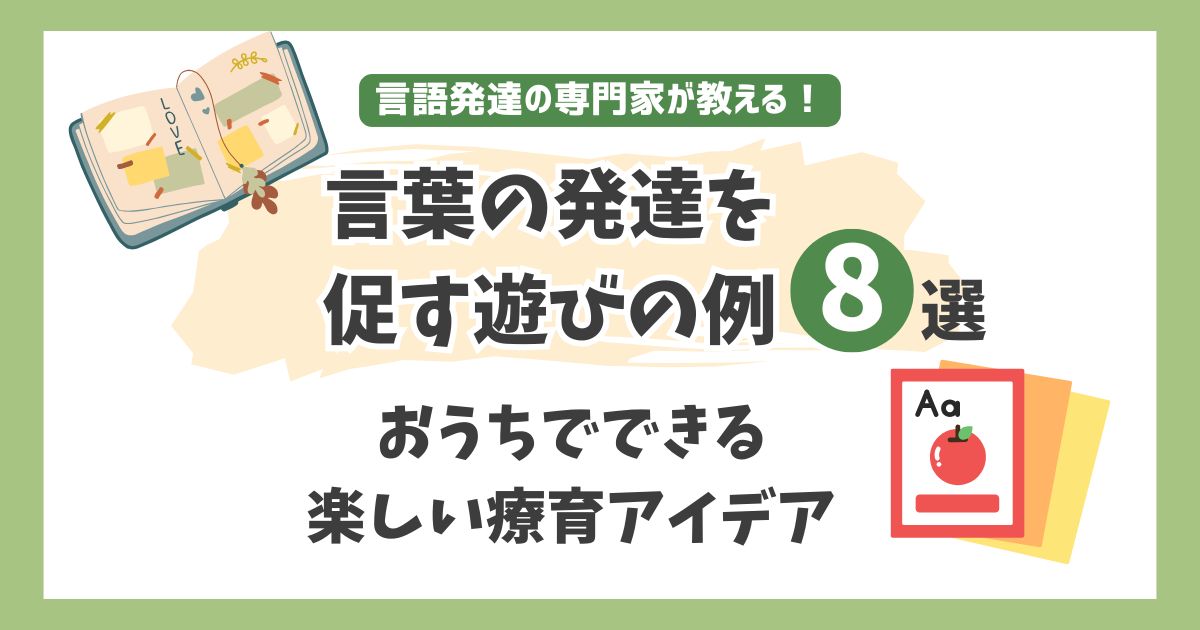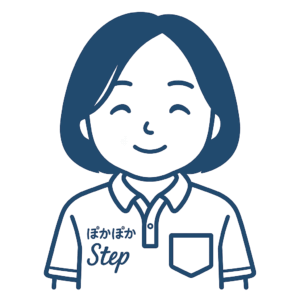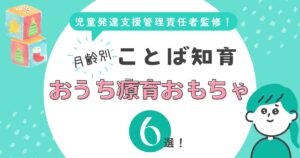「言葉の発達が少し遅いかも…」と感じたとき、家庭での遊びが大きな力になります。遊びながら自然に語彙や表現力、コミュニケーション力を伸ばす方法はたくさんあります。
本記事では、発達支援児への療育のプロである現役の児童発達支援管理責任者として、発達支援の現場でも効果があると言われる遊びの例や関わり方のコツをご紹介します。
遊びの中での関わり方や注意点、親としての心構えまで解説します。
言葉の発達を促す遊びの基本とポイント

遊びが言葉の発達に与える影響
遊びは、単なる娯楽ではなく、子どもが言葉を覚え、使いこなしていくための大切な「学びの場」です。
ごっこ遊びや絵本の読み聞かせなどを通して、子どもは新しい語彙や表現方法を自然に吸収します。
例えば、お店屋さんごっこをする中で「いらっしゃいませ」「これください」といったやりとりを繰り返すことで、状況に応じた会話や順序立てた発話の練習になります。
また、遊びの中では「失敗しても大丈夫」という安心感があるため、子どもが自発的に言葉を使いやすくなるのも特徴です。
発達支援の現場でも、遊びを通した言語刺激は、机上の学習よりも定着率が高いことがよくあります。
発達段階に合わせた遊び選びの重要性
子どもの言葉の発達には個人差があり、同じ年齢でも得意・不得意が異なります。
そのため、年齢や発達段階に合わせた遊び選びが重要です。
例えば、1〜2歳でまだ単語が中心の時期には、絵本やカードを使って身近な物の名前を知る遊びが効果的です。
3歳頃になり二語文や簡単な会話が増えてきたら、ごっこ遊びや質問ゲームなど、やりとりが発生する遊びを多く取り入れるとよいでしょう。
発達段階に合わない高度な言葉遊びを無理に行うと、子どもが遊びに集中できず、かえって自信を失うこともあります。
小さな成功体験を積み重ねられるよう、少し先のレベルを意識しながら遊びを設定しましょう。
安全で安心できる環境づくり
言葉の発達を促すためには、遊びの内容だけでなく環境づくりも大切です。
まず、子どもが安心して声を出せるよう、否定的な言葉を避け、「いいね」「教えてくれてありがとう」など肯定的な声かけを心がけましょう。
また、騒がしすぎる場所や刺激の多い環境では集中しにくくなるため、家庭での遊びは静かで落ち着ける空間がおすすめです。
さらに、遊び道具や絵本は子どもが手に取りやすい場所に置き、自分から選べるようにすると主体性が育ちます。
発達特性がある子の場合は、視覚支援(絵カードや写真)やタイマー(タイムタイマー)などを組み合わせて遊びの流れをわかりやすく示すことで、安心してやりとりに参加しやすくなります。
家庭でできる言葉を伸ばす遊びの例

①ごっこ遊び(ままごと・お店屋さんごっこ)
ごっこ遊びは、日常生活のやりとりを再現しながら言葉の使い方を学べる遊びです。
ままごとでは「ごはん作るね」「スープください」といった会話が自然に生まれます。
お店屋さんごっこでは、商品名ややりとりの順序を覚えることができ、順番や役割を理解する力も育ちます。
発達支援の現場では、子どもが好きなキャラクターや食べ物を小道具に取り入れると、集中力が高まり発話が増える傾向があります。
②絵本の読み聞かせ+質問タイム
絵本は語彙を増やすだけでなく、物語の流れや感情表現を学ぶ場にもなります。
読み聞かせの後に「この子はどんな気持ちだったかな?」「次はどうなると思う?」と質問を加えることで、想像力や表現力が育ちます。
文字数の多い絵本が難しい場合は、絵が大きくてセリフが少ない絵本から始め、徐々に文章量を増やしていくと負担が少なくなります。
③かるた・ことばカード
絵と文字が組み合わさったかるたやカードは、視覚情報と音声情報を同時に使うため、記憶に残りやすい遊びです。
「いぬ」「りんご」など身近な語彙から始め、少しずつ新しい単語を加えていきましょう。
チーム戦やタイムアタック形式にすると、ゲーム感覚で盛り上がりやすくなります。
④しりとりや言葉あそび歌
しりとりは、語彙力と発想力を同時に伸ばせる定番遊びです。
短い言葉しか出ない場合は「動物しりとり」「食べ物しりとり」などテーマを絞ると答えやすくなります。
歌に合わせて言葉を入れ替える「あそび歌」も、リズム感と発話の練習に効果的です。
⑤絵合わせやストーリーパズル
絵合わせカードやストーリー仕立てのパズルは、順序立てて説明する力を育てます。
例えば、パズルを完成させた後に「最初は○○、次は○○だったね」と話す練習をすると、出来事を順番に説明する構成力が鍛えられます。
⑥身近なもので「何かな?」クイズ
冷蔵庫の中やおもちゃ箱の中から1つ選び、袋や布で隠して「何かな?」と当てさせるクイズは、語彙と推測力を養います。
「冷たくて甘いものだよ」「丸くて赤いよ」などヒントを出すことで、形容詞や色、質感などの言葉も増えます。
⑦ブロックや積み木を使った説明ゲーム
ブロックや積み木で作った作品を「ここは窓で、ここはドア」と説明したり、相手の説明を聞いて同じ物を作る「見えないブロック遊び」も効果的です。
聞く力と説明する力の両方が鍛えられます。
⑧写真アルバムを見ながら話す
家族の写真や旅行の写真を見ながら、「これはどこ?」「何しているところ?」と話すと、過去の出来事を思い出しながら表現する練習になります。
経験と結びついた言葉は記憶に残りやすく、会話の幅が広がります。
遊びの中で意識したい関わり方

子どもの発話を待つ・引き出す質問
遊びの中では、大人が先に答えや言葉を提示しすぎず、子どもが自分で言葉を出す時間を確保することが大切です。
少し間をおく「待つ時間」を意識すると、子どもが考えて発話する機会が増えます。
例えば、絵本を読みながら「これは…?」と促し、子どもが答えるまで待つようにします。
 児発管いずみ先生
児発管いずみ先生「何色?」「どっちが大きい?」など、答えやすい質問から始めると会話のキャッチボールが続きやすくなります。
言葉を肯定的に受け止める
子どもが発した言葉は、正しい発音や言い回しでなくても、まずは肯定的に受け止めましょう。
「それ違うよ」ではなく「そうだね、○○とも言えるね」と、正しい言葉をさりげなく添えることで、否定される不安を減らしつつ自然な形で言葉を修正できます。
安心して話せる雰囲気は、発話意欲の向上に直結します。



間違った言葉遣いを自然な会話の流れで直すことを、
「リキャスト法」と言います。
繰り返しや言い換え(リキャスト法)の活用
リキャスト法とは、子どもの発話を大人が正しい形に直して繰り返す方法です。
例えば「わんわん、たべた」と言った場合、「そうだね、犬がごはんを食べたね」と正しい文にして返します。
これにより、正しい文法や語彙が自然に耳に入り、学びやすくなります。
発達支援の現場でも効果的とされる方法で、日常会話や遊びの中で繰り返し使えます。
視覚・聴覚など感覚を組み合わせる
言葉の理解や定着を促すには、視覚・聴覚・触覚など複数の感覚を組み合わせると効果的です。
例えば、果物カードを見せながら実物を触らせ、「これはりんご。赤くて丸いね」と話すと、感覚的な経験と語彙がリンクします。
特にASD傾向のある子や聴覚情報が入りにくい子には、視覚的なサポートが有効です。
発達特性に合わせた遊び方の工夫
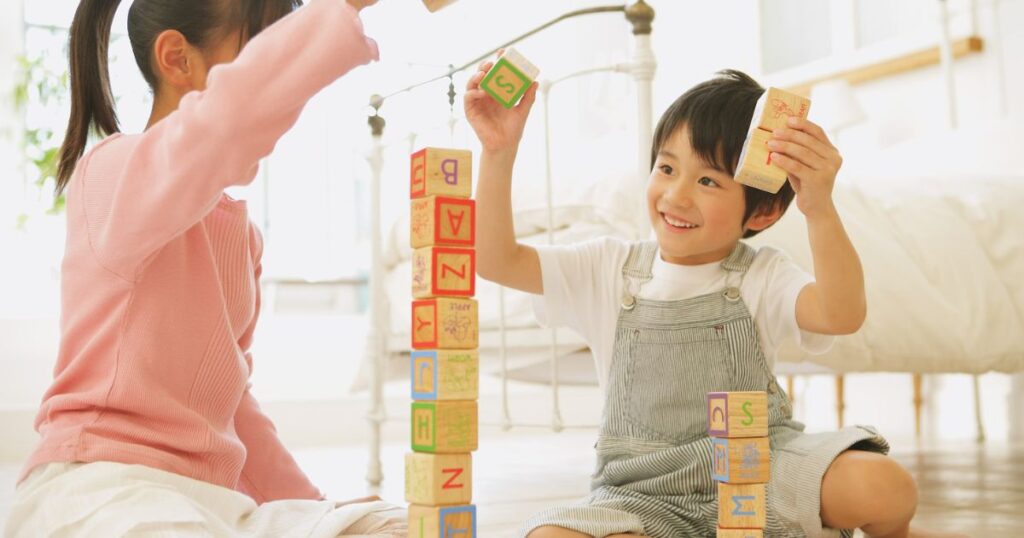
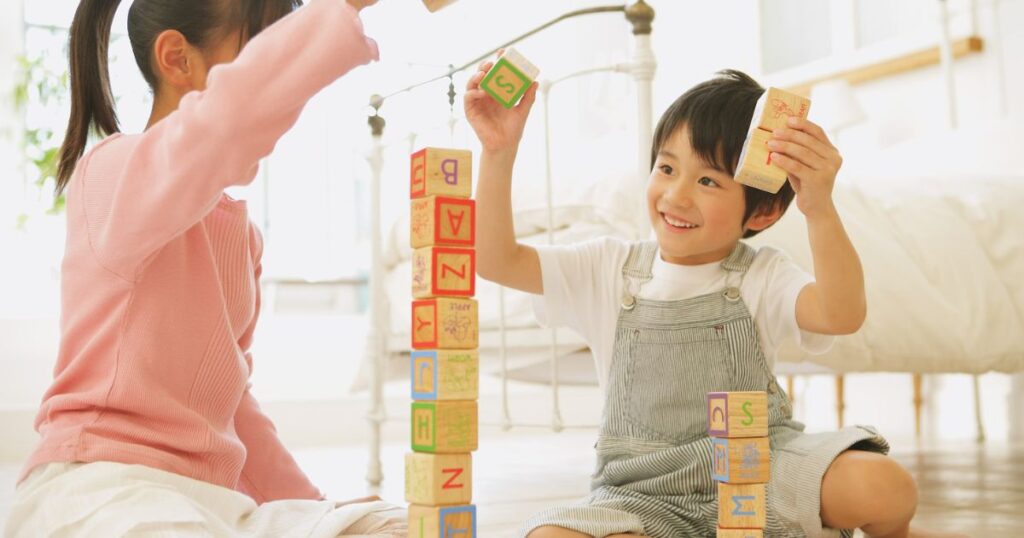
ADHD傾向のある子への工夫(短時間で区切る・動きを入れる)
ADHD傾向のある子は、長時間同じ遊びに集中するのが難しい場合があります。
そのため、遊びは5〜10分程度で区切り、テンポよく進めることがポイントです。
例えば、かるたやしりとりを数分ごとにテーマを変えて行う、ブロック遊びの中に「次は立ってジャンプしてから続けよう」といった動きを挟むと集中力が持続しやすくなります。
また、成功体験を多く積ませることで、自己肯定感が高まり遊びへの参加意欲も向上します。
ASD傾向のある子への工夫(視覚支援・順序の明示)
ASD傾向のある子は、見通しが立つと安心しやすくなります。
遊びの前に「①カードを配る→②読む→③取る」というように順序を絵や写真で提示すると、活動に入りやすくなります。
また、ルールが曖昧な遊びよりも、明確な手順やゴールがある遊びを選ぶと安心して取り組めます。
例えば、パズルや順番通りに並べるゲームは、構造化がしやすく理解も早まります。
言語発達遅滞のある子への工夫(反復・ゆっくりしたテンポ)
言語発達がゆっくりな子には、発話のテンポをゆっくりにし、同じ言葉を繰り返すことで定着を促します。
例えば、絵カードを見せながら「いぬ、いぬ」と繰り返し、子どもが言えたら「そう、犬だね」と肯定的に返すと安心感が生まれます。
また、一度に多くの言葉を覚えさせるより、少数の単語を繰り返し遊びの中で使う方が効果的です。
ジェスチャーや指差しなど、非言語的なサポートも組み合わせると理解しやすくなります。
遊びを通じた言葉の発達を支える親の心構え


成果を焦らず楽しむ姿勢
言葉の発達は個人差が大きく、数週間で急に伸びる子もいれば、ゆっくりと時間をかけて増えていく子もいます。
遊びを通して言葉を促すとき、大切なのは「今日何語覚えたか」よりも、「今日はどんなやりとりができたか」に目を向けることです。
焦って結果を求めると、子どもがプレッシャーを感じて発話意欲が下がってしまうこともあります。
親自身も「一緒に遊びを楽しむ」ことを第一に考えると、自然と会話が増え、結果的に言葉の習得につながります。
比較ではなく昨日の我が子と比べる
同じ年齢の子どもと比べて不安になる保護者は少なくありませんが、比べるべきは他の子ではなく「昨日までの我が子」です。
例えば、「昨日は“ワンワン”だけだったけど、今日は“ワンワン、きた”と言えた」など、小さな変化を喜ぶことで、子どもも自信を持ちやすくなります。
保護者が成長を見つけて褒める習慣を持つことで、子どもの自己肯定感も育まれます。
専門機関との連携と相談のタイミング
遊びを工夫しても、発話や理解の面で成長がなかなか見られない場合は、早めに専門機関へ相談することも大切です。
児童発達支援事業所や言語聴覚士(ST)などでは、家庭での関わり方や遊びのアレンジ方法もアドバイスしてくれます。
「相談=問題」ではなく、「成長の後押し」として専門家を頼ることが、子どもにとっても安心につながります。
また、家庭・園・専門機関が連携することで、一貫した関わりができ、言葉の発達がよりスムーズになります。
まとめ|遊びはことばの発達を育む最高の学び場
遊びは、子どもが安心してことばを試し、発達を促すための自然な学びの場です。
ごっこ遊びや絵本の読み聞かせ、カード遊びなど、日常の中で取り入れやすい方法でも十分に効果があります。
大切なのは、子どもの発達段階や特性に合わせた工夫をしながら、楽しいやりとりを積み重ねることです。
また、成果を急がず、昨日の我が子と比べて小さな成長を喜び合う姿勢が、子どもの自己肯定感を高め、発話意欲を引き出します。
もし成長がゆっくりに感じられる場合も、専門機関との連携を前向きに活用することで、より安心して子育てを進められるでしょう。



日々の遊び時間が、子どもの未来につながる大切な言葉の土台づくりになります。
私がいるぽかぽかステップこ・と・ばでは、ことば特化型の児童発達支援・放課後等デイサービスとして、ことばに難しさを抱えるお子様に支援を行っております。
体験・見学は下記のフォームからお申し込みください!