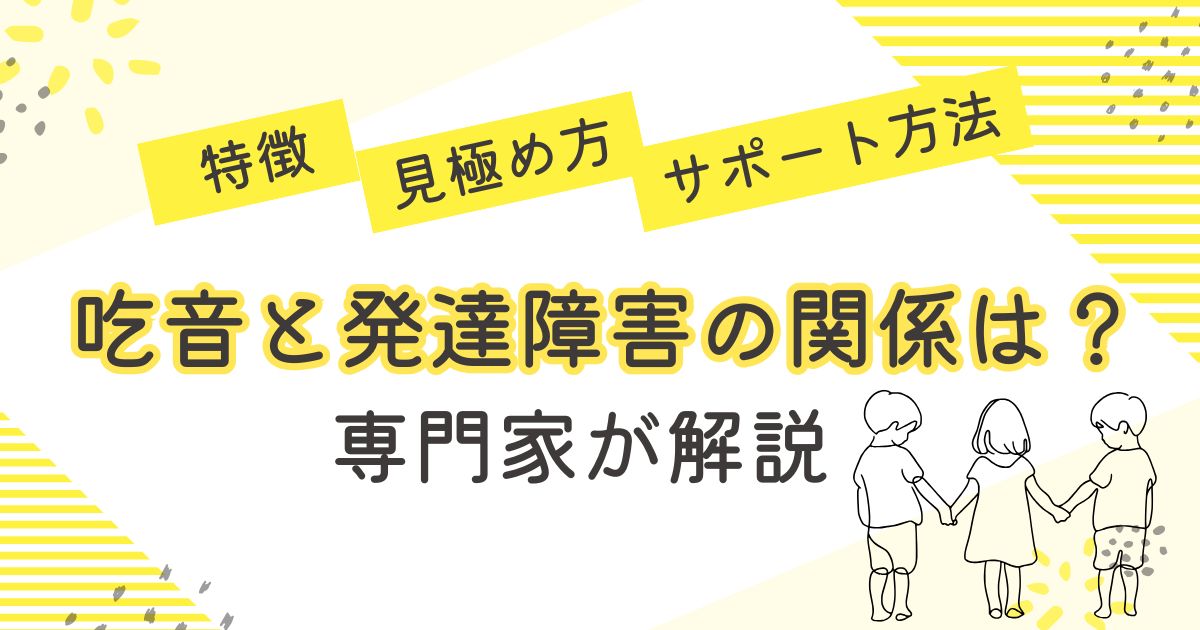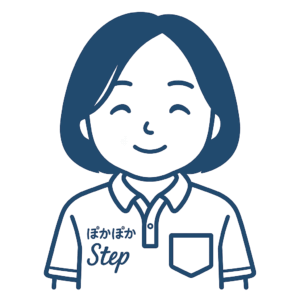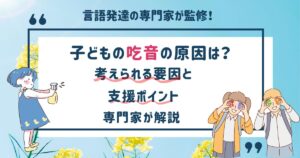「言葉がつっかえる」「話し始めがスムーズにいかない」などの吃音は、幼児期から小学生ごろにかけて見られることがあります。
中には「発達障害と関係があるのでは?」と心配する保護者や先生も少なくありません。
本記事では、ことば特化型の児童発達支援事業所で多くの子どもを支援してきた児童発達支援管理責任者が、吃音と発達障害の関係性、見極めのポイント、そして日常生活や学習場面での支援方法について詳しく解説します。
吃音とは?症状と種類
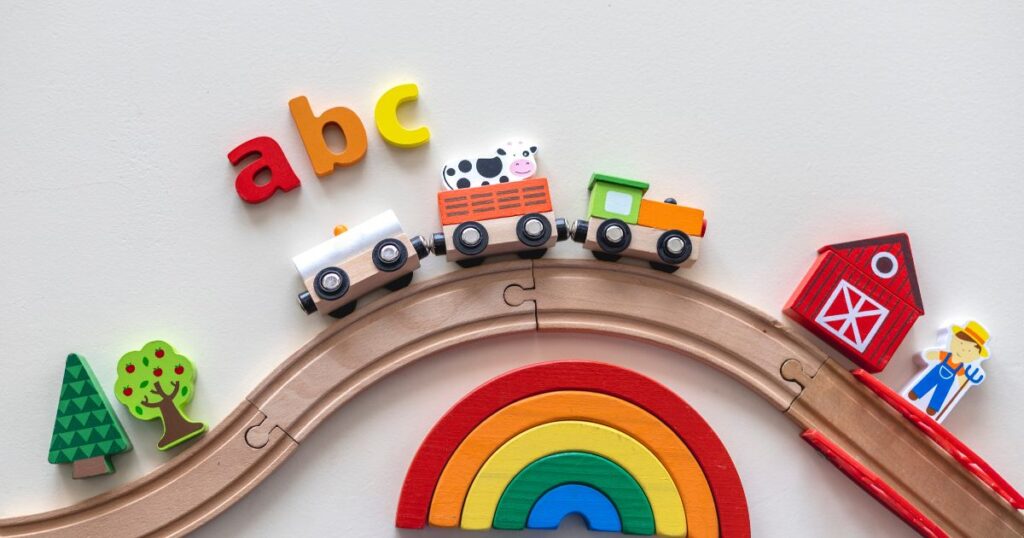
吃音の主な症状(繰り返し・引き伸ばし・詰まり)
吃音は、話し言葉がスムーズに出にくくなる言語の流暢性の障害です。代表的な症状には以下の3つがあります。
1.繰り返し(連発)
音や語を何度も繰り返す状態です。例:「あ、あ、あのね」「ぼ、ぼくは」など。
2.引き伸ばし(伸発)
音を不自然に長く伸ばす状態です。例:「あーーーのね」「そーーーして」など。
3.詰まり(ブロック)
話そうとしても声が出ず、言葉が詰まったようになる状態です。例:口は動いているのに音が出ない、息が詰まる。
これらの症状は単独で出る場合もあれば、組み合わさって現れることもあります。また、緊張や注目を浴びる場面、急いで話そうとする場面で強く出る傾向があります。
発症年齢と経過の一般的な傾向
吃音は多くの場合、2〜5歳ごろの言葉が急速に増える時期に発症します。
この時期は脳の言語領域が発達途上であり、言葉の組み立てが追いつかず、一時的に滑らかに話せなくなることがあります。
統計的には、幼児期に発症した吃音の約6〜8割は自然に改善します。
改善しやすいのは、発症から時間が経っていない場合や、家庭・園・学校で安心して話せる環境が整っている場合です。
一方、発症から長期間続いている場合や、本人が吃音を強く意識して避ける行動が見られる場合は、専門的な支援が必要となります。
一時的な吃音と慢性的な吃音の違い
一時的な吃音(発達性吃音)は、言葉の発達段階で一過性に現れるもので、多くは数か月〜1年程度で軽快します。
この場合、本人はあまり吃音を気にしていないことが多く、会話の中でも自然に話し続けられます。
慢性的な吃音(持続性吃音)は、発症から1年以上経っても症状が続くもので、思春期や成人まで残る場合もあります。
慢性化すると、吃音への不安や回避行動(話す場面を避ける、言い換えを多用する)が増え、学習や社会生活にも影響することがあります。
早期に専門家の評価を受け、必要に応じて介入することで、慢性化を防ぎやすくなります。
特に園や学校での様子、家庭での会話のしやすさなど、日常生活全体を含めた観察が大切です。
吃音と発達障害の関係

吃音は必ずしも発達障害とセットで起こるものではありません。
しかし、発達障害のある子どもに吃音が併存するケースは一定数あり、背景や対応の仕方に違いがあります。
ここでは、代表的な発達障害との関連性を解説します。
ASD(自閉スペクトラム症)との関連性
ASDの子どもは、言語の発達や会話の流れに独特の特徴を持つことがあります。
例えば、話題の切り替えが苦手、同じ言葉を繰り返す(エコラリア)、抑揚が平坦になるなどです。これらは吃音の繰り返しや詰まりとは異なりますが、ASDの子どもでも発達性吃音を伴うことがあります。
ASDに吃音が併存する場合、発話の流暢性だけでなく、コミュニケーション全体のスキル向上が必要です。
会話の相手の表情や反応を読み取る練習、話の順序を整理する支援などが有効です。
ADHD(注意欠如・多動症)との関連性
ADHDの特性である「衝動的に話し始める」「思いついたことをすぐ言おうとする」傾向は、吃音症状を強める場合があります。
特に詰まりや言葉の繰り返しが、急いで話す場面で目立つことがあります。
ADHDの子どもへの支援では、話すテンポを落とす練習や、深呼吸・視覚的合図を使って話し始めのリズムを整える方法が役立ちます。また、周囲が発話を急かさず、話し終えるまで待つ姿勢も重要です。
LD(学習障害)との関連性
LDの中でも読み書きの困難がある場合、話す内容を頭の中で整理するのに時間がかかり、その間に詰まりや引き伸ばしが生じることがあります。
特に音読や発表など、人前での発話場面で吃音が目立ちやすくなります。
LDと吃音が併存する場合は、言語処理の負荷を減らす工夫が有効です。
例えば、発表前に原稿を用意する、視覚資料を活用する、話す量を調整するなどが考えられます。
吃音から発達障害を疑うべきサイン
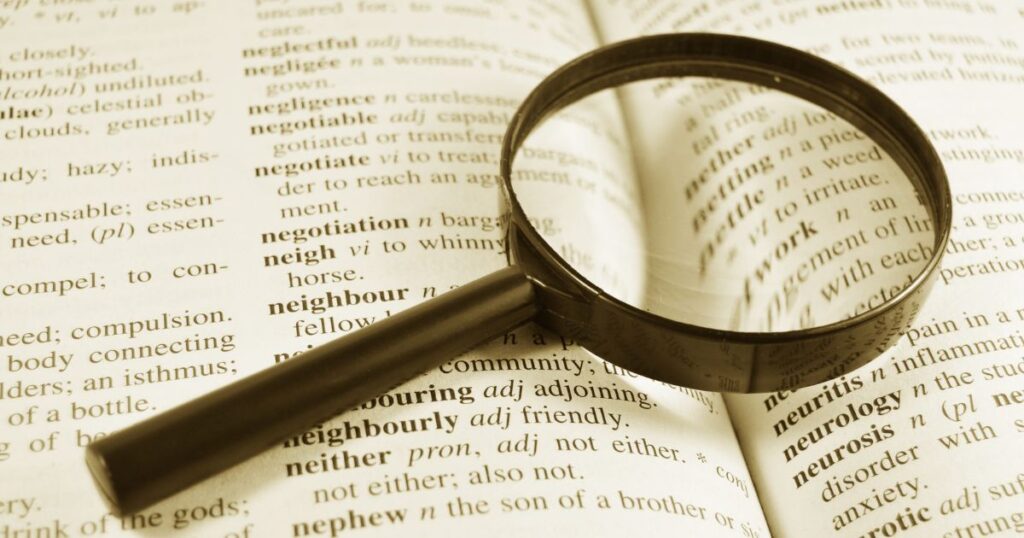
吃音があるからといって必ず発達障害があるわけではありません。
しかし、言葉の流暢さ以外にも発達面で特徴的な様子が見られる場合は、発達障害が併存している可能性があります。ここでは、相談や評価を検討する際の目安となるサインを挙げます。
言葉以外の発達面にも遅れや偏りがある
例えば、同年代の子に比べて手先の不器用さが目立つ、動作がぎこちない、数や色の理解が遅れているなど、複数の発達領域に課題が見られる場合は注意が必要です。
発達障害がある場合、言語だけでなく運動・認知・社会性などにも偏りが出ることが多く、吃音はその一部として現れることがあります。
コミュニケーションや社会性に課題がある
相手の話を順番に聞くのが難しい、話題の切り替えが極端に苦手、冗談や比喩が理解しづらいといった特徴がある場合、ASDやADHDの可能性が考えられます。
吃音だけであれば発話以外のやり取りはスムーズですが、発達障害が併存すると会話全体のやり取りや関係構築に課題が見られることがあります。
感覚過敏やこだわりが強い
音や光、触覚などに強く反応する、特定の順番やルールに強くこだわるといった様子も発達障害の特徴の一つです。
例えば、教室の雑音が気になりすぎて話せなくなる、好きな話題しか話したがらないなどが挙げられます。
こうした感覚やこだわりは、吃音の症状を強める要因にもなります。
日常生活や学習に大きく影響している
吃音のために発表や音読を避ける、友達との会話を控える、指名されると強い不安を感じるなど、学校や園での活動に影響が出ている場合は早期の支援が必要です。
発達障害が併存していると、不安感や自己評価の低下が進みやすく、学習意欲や社会参加にも影響します。
こうしたサインが複数見られる場合、まずは発達相談窓口や言語聴覚士、児童発達支援事業所など、専門機関での評価を受けることが望ましいです。
早期に特性を理解し、適切なサポートを始めることで、吃音やそれに伴う心理的負担を軽減できます。
発達障害がない場合でも吃音は起こる
吃音は発達障害とは無関係に発症することも多く、特に幼児期の一時的な吃音は発達障害を伴わない場合がほとんどです。
重要なのは、「吃音がある=必ず発達障害」というわけではないことです。
ただし、言葉以外の発達面(社会性、感覚、行動面)にも気になる点がある場合は、早めに専門機関に相談し、発達全体の評価を受けることが望ましいです。
吃音がある子への支援の基本

吃音のある子どもにとって、最も大切なのは「安心して話せる環境」を整えることです。
症状そのものをすぐに消すことは難しくても、適切な関わりによって症状が軽くなったり、話す意欲を保ったりすることができます。
ここでは、日常でできる支援の基本を紹介します。
安心できる話しやすい環境を作る
吃音は緊張や不安で悪化しやすいため、落ち着いて話せる雰囲気をつくることが大切です。
- 話している途中で他の人が話し始めない
- 注目されすぎないように、発表や音読の場面を工夫する
- 雑音や視覚的な刺激を減らす(教室の掲示物、テレビ音など)
療育や教室でも、パーテーションや席の配置を工夫して、周囲の刺激を減らすことが有効です。
発話を急かさない・遮らない
「早く言って」「もっとはっきり」と急かすことは、吃音のある子にとって大きなプレッシャーになります。
言葉が詰まっても、最後まで話し終えるのを待つ姿勢が重要です。
また、言葉を代わりに言ってしまうと本人の達成感が得られにくくなるため、できるだけ本人の力で話しきれるように支援します。
言葉以外の表現手段を活用する
吃音の症状が強い時期や場面では、絵やジェスチャー、筆談、カードなど、言葉以外の方法も使えるようにしておくと安心です。
例えば、授業での回答を絵やカードで示す、友達とのやり取りで指差しや表情を活用するなど、本人の負担を減らしながら意思疎通を続けられる工夫が効果的です。
 児発管いずみ先生
児発管いずみ先生ぽかぽかステップこ・と・ばでは、
はじめはカード等を使用して、二択から
自分の意思表示をしてもらいます。
成功体験を積ませて自信を育てる
吃音があっても「話しても大丈夫」という経験が増えると、話す意欲が高まります。
- 少人数の場面で発表する機会を作る
- 得意な話題を自由に話す時間を設ける
- 話せたときはすぐに褒める
成功体験は「話すこと=楽しい」という感覚につながり、長期的に自信を支える土台になります。
専門機関や療育でのサポート


吃音が長く続いたり、日常生活や学習に影響が出ている場合は、専門機関や療育サービスの活用を検討しましょう。
専門家による評価や練習、環境調整は、症状の軽減と本人の安心感につながります。
言語聴覚士による発話支援
言語聴覚士(ST)は、ことばや発音の専門家です。吃音のある子には、
- 呼吸のリズムを整える練習
- ゆっくり話す練習(スロースピーチ)
- 声を出しやすい姿勢や発声法
などを指導します。
また、吃音の症状や傾向を客観的に評価し、家庭や学校に合ったアドバイスを提供してくれます。
児童発達支援・放課後等デイサービスでの支援
ことばの発達やコミュニケーションに特化した児童発達支援や放課後等デイサービスでは、遊びや学習を通じて発話を促すプログラムが行われます。
- 少人数や個別での会話練習
- 友達とのやり取りを支えるソーシャルスキルトレーニング(SST)
- 学校生活で必要な発表や音読の練習
こうした場は、本人が「話すこと」に慣れる安全な練習の場として有効です。
学校や園との連携方法
吃音のある子どもが学校や園で安心して過ごせるように、担任や支援員と情報共有を行いましょう。
- 発表や音読の順番を事前に知らせる
- 無理に指名せず、希望制にする
- 話しやすい少人数グループを設定する
療育や医療機関で得たアドバイスを学校にも伝えることで、家庭・療育・学校が一貫した支援を行えます。
家庭でできる練習や関わり方
専門機関で教わった方法を家庭でも繰り返すことで、定着が早まります。
- ゆっくり話す習慣を家族全員で意識する
- 話した内容を否定せず受け止める
- 詰まっても表情や態度で安心感を与える
家庭での温かい関わりは、吃音のある子どもにとって最も心強い支えとなります。
まとめ│原因を知り、安心できる環境づくりから始めよう
吃音は、言葉の流暢さに影響する症状であり、繰り返し・引き伸ばし・詰まりといった特徴があります。発症は2〜5歳ごろが多く、一時的に改善する場合もあれば、長く続く場合もあります。
発達障害(ASD・ADHD・LD)と併存することもありますが、吃音がある=必ず発達障害というわけではありません。判断には、言葉以外の発達面やコミュニケーション、感覚の特性なども含めた総合的な観察が必要です。
支援の基本は、安心して話せる環境づくり、発話を急かさない姿勢、言葉以外の表現手段の活用、そして成功体験の積み重ねです。必要に応じて、言語聴覚士や児童発達支援・放課後等デイサービス、学校との連携を行いましょう。
早期に特性を理解し、家庭・学校・専門機関が一体となった支援を行うことで、吃音やそれに伴う心理的な負担を軽減し、子どもが安心して言葉を育んでいける環境を整えることができます。
私がいるぽかぽかステップこ・と・ばでは、ことば特化型の児童発達支援・放課後等デイサービスとして、ことばに難しさを抱えるお子様に支援を行っております。
体験・見学は下記のフォームからお申し込みください!