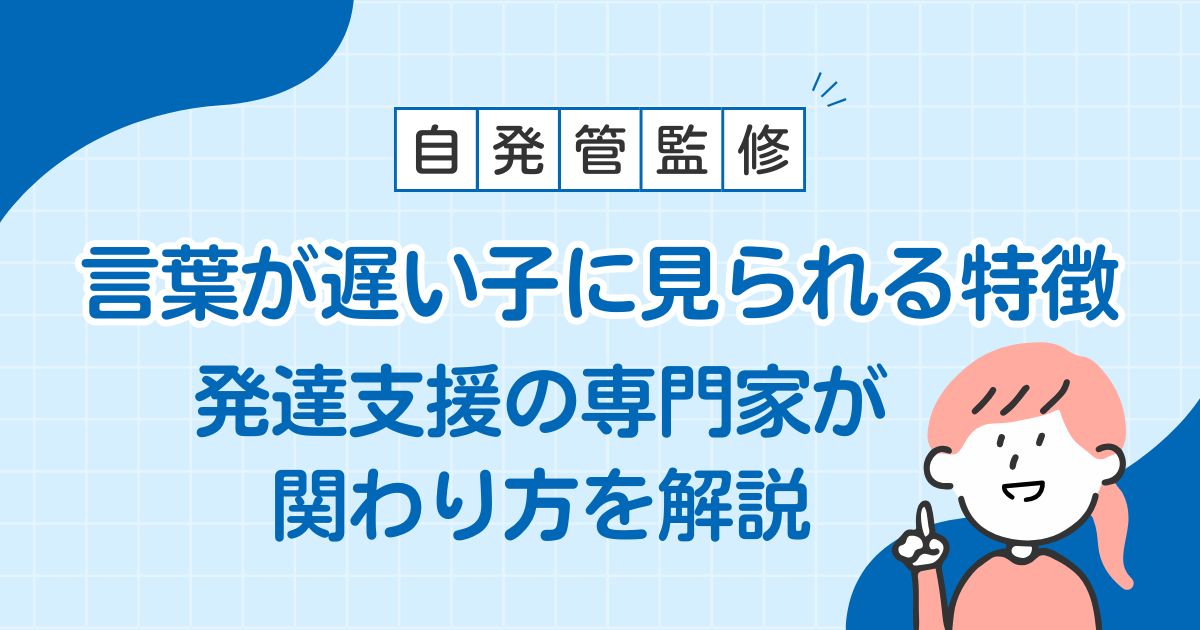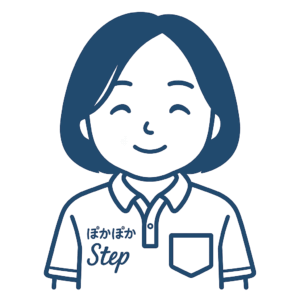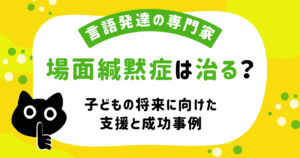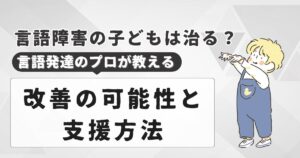言葉が遅いと感じる子どもに見られる特徴や、その背景にある可能性を解説します。
発達障害との関係や言葉が急に伸びるタイミング、関わり方の工夫まで、児童発達支援管理責任者の視点からまとめます。
言葉が遅い子に共通する特徴とは

言葉が遅い子どもには、いくつか共通して見られる傾向があります。
ただし、これらは必ずしも発達障害や重大な問題を意味するものではなく、成長のペースや環境によっても変化します。ここでは、児童発達支援管理責任者として現場で多くの子どもを見てきた経験から、よく見られる特徴を具体的に紹介します。
発語が少ない・単語数が増えにくい
年齢に応じた語彙数の伸びがゆるやかで、「あ!」「ママ」など限られた言葉しか使わない時期が長く続くことがあります。
例えば2歳を過ぎても単語数が10語程度にとどまっている場合や、新しい言葉を覚えてもすぐに使わなくなるケースも見られます。
背景には、発話への興味が薄い、音声模倣が苦手、耳から入る情報を処理するのに時間がかかるなどの要因があります。
発音が不明瞭で伝わりにくい
話す意欲はあっても、発音がはっきりせず周囲に伝わりにくい場合があります。
例えば「さかな」が「たかな」になる、「くるま」が「くま」になるなど、音の省略や置き換えが目立つことがあります。
これは口や舌の動きの発達段階や筋力の弱さ、音の聞き分けの難しさなどが関係します。不明瞭な発音は本人にとって「伝わらない」体験となり、発語意欲の低下につながることもあります。
指差し・ジェスチャーなど非言語のやり取りが少ない
言葉の発達と並行して育まれるのが、指差しや手振り、表情などの非言語コミュニケーションです。
これらが少ない場合、周囲と「共有する」経験が不足し、言葉を使ったやり取りの土台が育ちにくくなります。
例えば、見つけた物を指差して知らせたり、「ちょうだい」と手を伸ばしたりといった行動が乏しい場合は、言葉以前の関わり方を丁寧に育てる必要があります。
会話のキャッチボールが続かない
一問一答で終わってしまい、会話が長く続かないことも特徴の一つです。
質問に対して単語で答えるだけ、返答までに時間がかかる、相手の話に関連づけて話題を広げられないなどが見られます。
この背景には、語彙不足だけでなく、相手の話の意図を理解する力や、やり取りの経験の少なさが関係します。会話のキャッチボールは、日常の中での繰り返しや、安心できる関係性の中で育まれていきます。
特徴から考えられる背景や要因

言葉が遅い子どもには、それぞれ異なる背景や理由があります。
単に「遅れている」と判断するのではなく、どのような要因が関わっているかを理解することが、適切な関わりやサポートの第一歩です。
ここでは、現場でよく見られる主な背景を4つに分けて解説します。
個人差による一時的な遅れ
言葉の発達は、歩く・食べるなどの運動発達と同様に、子どもによってペースが異なります。
中には、運動や感覚遊びに興味が強く、言葉より体を動かすことを優先するタイプの子もいます。
この場合、成長とともに言葉が自然に増えることも少なくありません。
また、兄姉がよく話してくれる環境では、本人が話さなくても周囲が察してくれるため、発話の必要性を感じにくいこともあります。
聴覚や口腔機能の影響
耳の聞こえにくさ(滲出性中耳炎など)や、舌・口の動きの制限(舌小帯短縮症など)があると、音の聞き取りや発音が難しくなります。
聞き取りづらい音は再現しにくく、発音が不明瞭になることで語彙の習得も遅れがちです。
耳鼻科や小児科での検査によって、早期に対処できる場合もあります。
環境要因(家庭での会話量・刺激の有無)
日常的に言葉のやり取りが少ない環境では、発話の機会が減ります。
テレビや動画からの受動的な刺激はあっても、双方向の会話が少ないと、言葉を使う経験が育ちにくくなります。
また、忙しさや生活リズムの乱れによって、落ち着いて関われる時間が不足している場合も、発達に影響を与えることがあります。
発達障害(ADHD・ASD・LD)との関連性
言葉の遅れは、発達障害の特性の一部として現れることもあります。
- ASD(自閉スペクトラム症):社会的なやり取りの難しさや、言葉よりも視覚・感覚情報に注目する傾向から、発話の発達がゆるやかになることがあります。
- ADHD(注意欠如・多動症):注意が安定せず、会話や模倣に集中する時間が短いことで、言葉の習得が遅れる場合があります。
- LD(学習障害):音の聞き分けや言語処理に困難があり、特定の音や単語を覚えにくい傾向があります。
発達障害が背景にある場合のサイン

言葉の遅れは成長の個人差であることも多いですが、発達障害の特性の一部として現れる場合もあります。
早期に適切な支援につなげるためには、「気になるサイン」を見逃さないことが大切です。ここでは、現場でよく見られる傾向を具体的に紹介します。
言葉以外の発達にも遅れや偏りがある
発達障害が背景にある場合、言葉だけでなく、運動や社会性など他の領域にも遅れや凸凹が見られることがあります。
例えば、同じ年齢の子に比べて走る・ジャンプするといった動作が遅れている、または逆に特定の動作だけ極端に得意などの偏りがあるケースです。こうした全体的な発達の様子を総合的に見ることが大切です。
こだわりが強い・感覚過敏がある
決まった遊び方や順序にこだわる、服のタグや特定の音・光を極端に嫌がるなど、感覚の過敏さや行動のこだわりが強く見られることがあります。
こうした特徴があると、言葉を使ったやり取りの経験が限られ、コミュニケーションの発達に影響する場合があります。
集団でのやりとりや模倣が少ない
同年代の子どもの動きや遊びを真似しない、集団遊びよりも一人遊びを好むなど、社会的なやり取りの機会が少ないことがあります。
模倣は言葉の習得にとても重要で、他者の動作や発話を真似することで語彙や表現が増えていきます。そのため、模倣の少なさは言葉の遅れにつながることがあります。
目線が合いにくい・呼びかけへの反応が乏しい
名前を呼んでも振り向かない、目線が合う時間が短いなど、相手への関心や注意の向け方に特徴が見られる場合があります。
視線や反応の少なさは、相手とのやり取りの土台を築きにくくし、言葉を使う機会を減らす要因となります。これはASDの傾向を持つ子によく見られるサインです。
言葉が急に伸びる場合の兆候ときっかけ

言葉の発達は一直線ではなく、しばらく停滞していたのに、ある日を境に急に語彙や会話が増えることがあります。
この「伸びるタイミング」にはいくつかの共通点や背景があり、日々の関わりの中で兆候をキャッチすることで、成長を後押しするサポートがしやすくなります。
好きな遊びや興味が会話のきっかけになる
子どもが夢中になれる遊びやキャラクター、出来事が見つかると、それを人に伝えたい気持ちが強くなります。
例えば電車好きの子が、駅や車両を指差しながら「でんしゃ!」「あか!」などと言葉を発するようになるケースです。興味のある対象は、発話意欲を高める大きな原動力になります。
環境や関わり方の変化
引っ越しや入園、きょうだいとの関わりなど、生活環境が変わったことをきっかけに、言葉が増えることがあります。
特に新しい人との交流や、刺激の多い環境に触れることで、これまで蓄積されていた理解が一気に表出されることがあります。逆に、安心できる環境に落ち着いてから話し始めるタイプの子もいます。
発達段階の成熟
運動能力や認知力、記憶力などが一定の水準に達すると、それまでうまく表現できなかった言葉が急に出てくることがあります。
これは脳の発達によるもので、特に2〜3歳頃は発達の伸びが顕著に現れやすい時期です。
「昨日は単語だったのに、今日は二語文になっている」など、短期間での変化も少なくありません。
モデルとなる人との関係性の変化
保育士や親、きょうだいなど、子どもが「この人と話したい」と思える相手の存在は大きな影響を与えます。
信頼関係が深まり、安心して話せる環境が整うと、言葉のやり取りが活発になりやすいです。
また、同年代の友達からの刺激も大きく、「友達の真似をしたい」気持ちが発話を促すことがあります。
関わり方の工夫とサポート方法

言葉が遅いと感じる子どもへの関わりは、「話させる」ことを急ぐのではなく、安心してやり取りできる環境をつくることが基本です。
日常の中で少しずつ発語の機会を増やし、楽しみながら言葉を育てていくことが大切です。
日常生活に言葉を取り入れる
ご飯を食べるときや着替えをするときなど、生活のあらゆる場面で言葉を添える習慣をつけましょう。
例えば「ごはんだよ」「くつはくよ」「あかいくつだね」など、行動や物の名前を実況中継するように話しかけることで、言葉と意味の結びつきが強くなります。
繰り返し聞くことで、子どもが自然に覚えやすくなります。
発語を促す遊びや活動を取り入れる
歌や手遊び、絵本の読み聞かせ、簡単なごっこ遊びなどは、発語のきっかけになりやすい活動です。
特に、同じフレーズを繰り返す歌や、音を楽しめる絵本は、言葉の模倣を促します。
また、動物や乗り物の名前を当てるカード遊びなども効果的です。
子どもの発信に対して肯定的に応答する
発音が不明瞭でも、言葉の一部しか聞き取れなくても、「○○って言ったんだね」「そうだね!」と肯定的に返すことが重要です。
正しい発音をすぐに求めるよりも、「伝わった」経験を積むことで、話す意欲が高まります。
子どもの言葉を少し広げて返す「リキャスト法」もおすすめです。
 児発管いずみ先生
児発管いずみ先生リキャスト法は、子どもの間違いを自然な会話の中で直す方法です。
たとえば「これ わんわん」に対して、
「そうだね。あれは犬だね」と返し、子どもに正しい語彙や語順、助詞などを教えます。
必要に応じて専門機関に相談する
3歳を過ぎても二語文が出ない、言葉以外の発達にも遅れや偏りがある、対人反応が乏しいなど、気になる点が複数ある場合は、早めに専門機関に相談しましょう。
発達相談センター、小児科、耳鼻科、児童発達支援事業所などでは、発達評価や適切な支援の提案を受けられます。
早期のサポートは、言葉だけでなく全体的な成長にも良い影響を与えます。
まとめ|特徴を知って適切な関わりで言葉の発達を後押ししよう
言葉が遅い子どもには、発語の少なさや発音の不明瞭さ、非言語コミュニケーションの少なさ、会話のやり取りが続きにくいといった共通の特徴が見られることがあります。
その背景には、成長の個人差や一時的な遅れ、聴覚や口腔機能の問題、環境要因、さらには発達障害の特性など、さまざまな要因が関係しています。
一方で、好きなことを見つけたり、環境が変わったり、信頼できる人との関係が深まったことをきっかけに、言葉が急に伸びるケースもあります。
日常生活の中で言葉を取り入れる工夫や、肯定的な応答、遊びを通したやり取りを重ねることが、言葉の発達を後押しします。
「もしかして遅いのかな?」と感じたら、無理に話させようとするのではなく、安心して表現できる環境を整え、必要に応じて専門機関に相談することが大切です。
特徴を正しく理解し、子どものペースを尊重しながら関わることが、将来の豊かなコミュニケーションにつながります。
私がいるぽかぽかステップこ・と・ばでは、ことば特化型の児童発達支援・放課後等デイサービスとして、ことばに難しさを抱えるお子様に支援を行っております。
体験・見学は下記のフォームからお申し込みください!