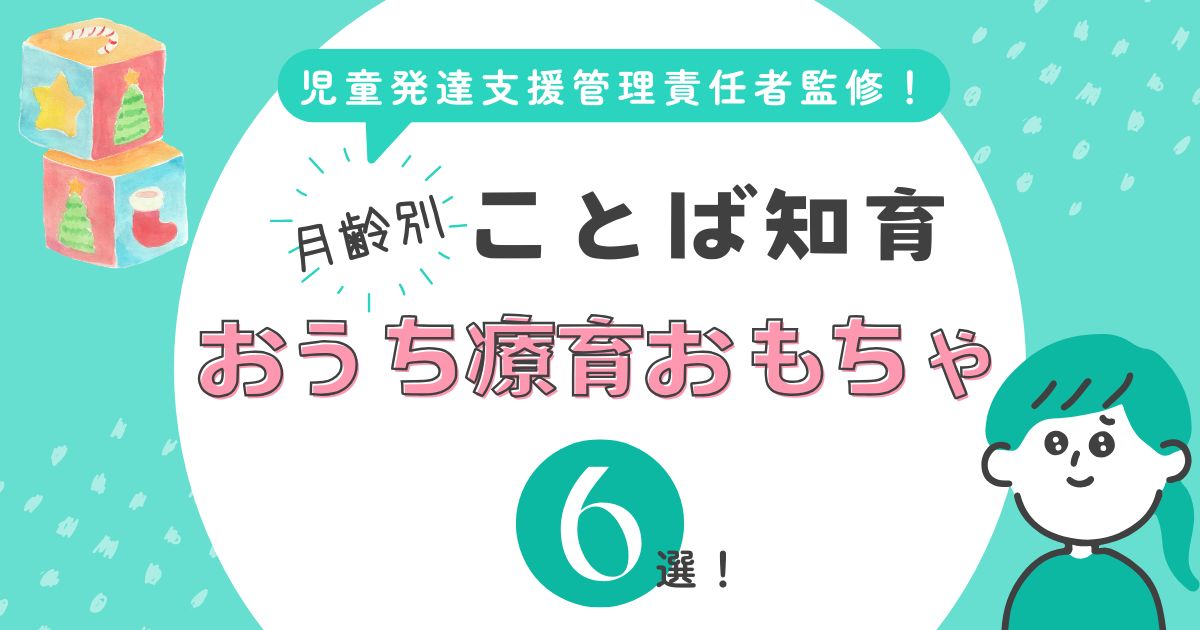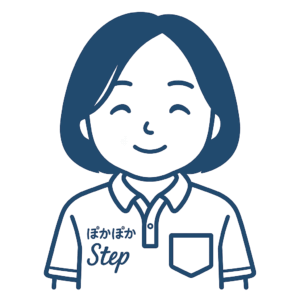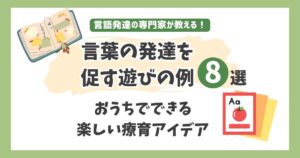言葉の発達には個人差があるが、遅れが気になるときに家庭でできる知育方法を知りたい保護者は多いです。
本記事では、言葉が遅い子の特徴、家庭でできる月齢別知育遊び、効果的なおもちゃ、そして支援機関の活用法までを解説していきます。
児童発達支援管理責任者としての経験から、現場での支援事例やアドバイスも交えてお伝えします。
言葉の発達の基礎知識
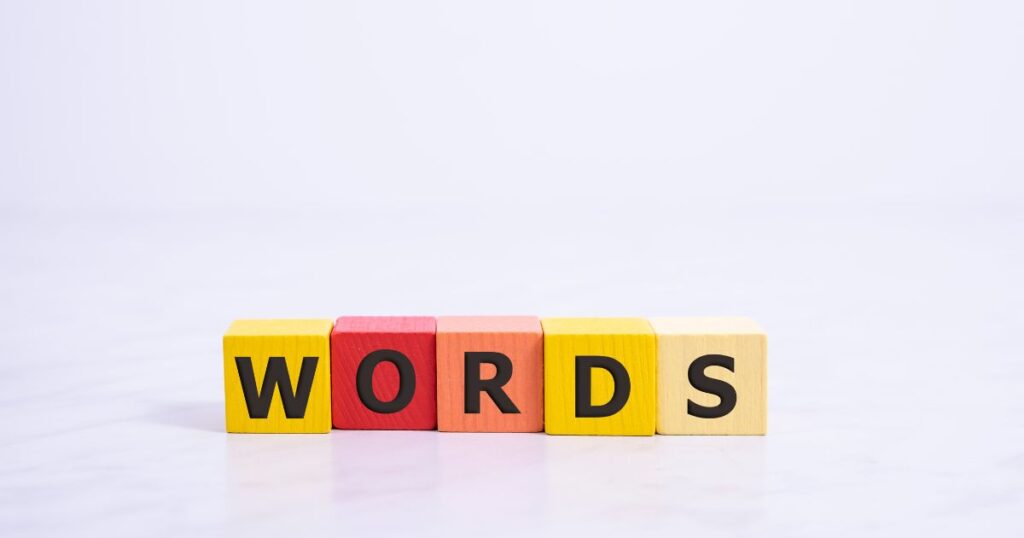
ことばの発達と脳の発達の関係
ことばの発達は、脳の成長と密接に関係しています。
脳の中では「聞く」「理解する」「話す」といった言語機能が、乳幼児期から段階的に発達します。
特に0〜3歳頃は「言語の臨界期」と呼ばれ、音や言葉のインプットが非常に重要な時期です。
この時期に周囲の人から語りかけを多く受けたり、さまざまな音や単語に触れることで、脳の中に言語のネットワークが形成されていきます。
一方で、ことばの習得は「耳からの情報処理」だけではなく、動作や表情、視覚的な情報など多様な感覚の連携によっても促進されます。
たとえば、手遊び歌や絵本の読み聞かせは、聴覚・視覚・運動感覚を同時に刺激するため、ことばの獲得に効果的です。
言葉が遅れる原因(環境要因・性格・発達特性など)
言葉の発達には個人差がありますが、その背景にはいくつかの要因があります。
環境要因としては、周囲の大人との会話や語りかけが少ない、テレビやタブレットからの一方的な情報が多いなど、双方向のコミュニケーションが不足している場合が挙げられます。
性格的要因では、おとなしく慎重なタイプの子は、頭の中で十分に言葉を整理してから話そうとするため、発語が遅く見えることがあります。
また、逆に活発で行動優先のタイプの子は、動きで意思を伝えることが多く、言葉の表出がゆっくりになることもあります。
発達特性としては、聴覚処理や言語理解の発達の遅れ、感覚過敏や鈍麻、注意の持続の難しさなどが、言葉の習得ペースに影響します。
これらが複合的に絡み合うため、「ただの個性」か「支援が必要な発達の遅れ」かを見極めるには、専門的な視点が重要です。
言葉の遅れと発達障害の関係
言葉の遅れは必ずしも発達障害を意味するものではありません。
しかし、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)、LD(学習障害)などの発達障害の特性の一部として、言葉の習得や使い方に特徴が見られる場合があります。
たとえばASDでは、言葉の模倣はできても会話のやりとりが続かない、オウム返しが多いなどの傾向が見られることがあります。
ADHDでは、言葉は出ていても話の順序が飛びやすく、相手の話を最後まで聞くのが難しい場合があります。
重要なのは、言葉の遅れが「日常生活や対人関係にどの程度影響しているか」です。
影響が大きい場合や年齢相応の伸びが見られない場合は、早めに発達相談や専門機関での評価を受けることが、その後の成長を支える大きな一歩となります。
月齢別|家庭でできる言葉の知育遊び

1歳頃(初語が出る時期)の遊び
1歳前後は、「ママ」「ワンワン」など初めての言葉(初語)が出やすい時期です。
ことばを育てるためには、五感を使った体験と、短い語の繰り返しが効果的です。
おすすめは、音や擬音を使ったやり取り遊びです。
たとえば、車の玩具を走らせながら「ブーブー」、犬のぬいぐるみを動かして「ワンワン」と声をかけると、耳からの音と目の前の動きが結びつきやすくなります。
また、顔や体の部位を指差して名前を伝える遊びも効果的です。
「おめめはどこ?」「おくちは?」と触れながら語りかけると、語彙の理解が進みます。この時期は「繰り返し」と「楽しい雰囲気」が最大のポイントです。
1歳半〜2歳頃(二語文が出始める時期)の遊び
1歳半を過ぎると、「ママ きて」「ワンワン いた」など二語文が出始めます。
この時期は単語の組み合わせを増やす遊びが有効です。
おすすめは、おままごとやごっこ遊びです。
お皿やお鍋を使って「ごはん どうぞ」「ジュース のんで」など、動作と言葉を組み合わせて遊びます。
また、「これなあに?」クイズも語彙を広げるきっかけになります。
絵本や身近な物を指差し、「これはなあに?」「なにいろ?」などと聞いて答えるやり取りを繰り返すことで、単語理解や色の概念が定着します。
3歳頃(会話が成立する時期)の遊び
3歳になると、簡単な会話が成立するようになり、「なんで?」「どうして?」という質問も増えてきます。
この時期におすすめなのは、絵本のストーリー予想です。
絵本を読みながら途中でページをめくる前に「次はどうなるかな?」と問いかけると、話の筋を考える力や表現力が養われます。
また、ジェスチャー遊びもおすすめです。
「動物まねっこゲーム」や「ポーズ当てゲーム」など、身振り手振りで表現する遊びを通じて、非言語的なコミュニケーション力とことばの結びつきが深まります。
4〜5歳頃(語彙が増える時期)の遊び
4〜5歳になると、語彙数が大きく増え、会話もスムーズになってきます。
おすすめは、しりとりや連想ゲームです。(しりとりを行うには「音韻」の理解、言葉は数個の音でできていることの理解が必要になってきます)
遊びながら語彙を増やし、音の意識も高められます。
また、簡単なルール遊び(すごろくやカードゲーム)も有効です。ルールを理解して言葉で説明したり、順番を守ったりする経験が、会話力と社会性の両方を育みます。
6歳頃(説明ができる時期)の遊び
6歳頃になると、経験を整理して相手に説明できる力が育ってきます。
この時期は、自分の経験を話す活動が効果的です。
「今日あったことインタビュー」や「好きなものプレゼンごっこ」など、テーマを決めて話してもらいます。
また、図鑑や写真を使った調べ学習ごっこもおすすめです。興味を持ったテーマについて調べ、わかったことを自分の言葉で説明することで、語彙と表現力の両方が伸びます。
言葉の発達を促す知育おもちゃの選び方とおすすめ7選

言葉の発達を支える知育おもちゃは、単なる遊び道具ではなく「ことばのきっかけ」になる大切なツールです。
ただし、発達段階や子どもの興味に合っていないと、逆に遊ばれず終わってしまうこともあります。
ここでは、言葉の発達を促す観点から選び方のポイントを紹介します。
 児発管いずみ先生
児発管いずみ先生こちらで紹介しているおもちゃはぽかぽかステップこ・と・ばで
実際に療育に使われていますので、ぜひ参考にしてくださいね。
音や声を楽しむおもちゃ
1〜2歳頃の初語期には、音や声が出るおもちゃが特に効果的です。
例としては、マイク付きのおもちゃ、動物の鳴き声が出る絵本、音が鳴る積み木などがあります。
音と物の動きが結びつくことで「音→意味」の理解が進みます。
また、録音再生ができるタイプのおもちゃは、自分の声を聞く体験にもなり、発音の意識づけにもつながります。
絵本やカード型教材
絵本はすべての年齢でおすすめできる言語発達の基盤アイテムです。
0〜2歳には、はっきりした色と大きな絵のシンプルな絵本、3歳以降はストーリー性のある絵本がおすすめです。
絵カード(動物・食べ物・道具など)は、語彙を増やすのに有効です。
「これなあに?」と聞いたり、「〇〇を取って」と指示を出す遊びで理解力と表現力を同時に伸ばせます。
ファンラーニング テルミー・ザ・ピクチャー
- 視覚・空間認知の発達
→ 「〜の前」「〜の左側」などの位置関係を表す言葉(空間認知)を、実際に絵を伝える体験を通して理解しやすくなります。この遊びを通して、空間概念の理解が育まれます。 - 予測力・見通しの育成
→ 相手にどう伝えるかを考え、また説明を聞いて同じ絵に仕上げることで、やり取りのステップが自然と見えてきて、見通しを持って行動する経験になります。 - 切り替えのサポート
→ コミュニケーションというゲームのステップ(聞く・説明する・描く)を通して、次の動作への切り替えが構造化されるため、不安なく次の活動に移行しやすくなります。 - 自己管理力・表現力・理解力の強化
→ 相手にわかるように伝えようとする「表現力」と、相手の説明を正しく受け取り理解しようとする「理解力」の両方が鍛えられます。成功体験を積むことで、自信と自己管理能力の向上も期待できます。



コミュニケーションを通して“表現する力”“理解する力”を育てながら、不安が減り、活動の切り替えがスムーズになり、自分で考えて伝える力が養われます。成功体験もたくさん積めます。
手先を使う遊びができるおもちゃ
手先を使う活動は、脳の前頭葉や感覚統合の発達を促し、言語発達にも良い影響を与えます。
ブロック、型はめパズル、紐通し、粘土などは、作ったものを説明することで会話のきっかけにもなります。
例えば「何を作ったの?」「これはどうやって作ったの?」と問いかけると、自分の考えを言葉にする練習にもなります。
くるくるチャイム
- 因果関係を理解する
→ 「玉を入れると転がる」「最後に音が鳴る」という原因と結果を体験的に学びます。 - 手の操作や協応動作の発達を促す
→ボールをつかむ・入れる・目で追うことで 手先の器用さや目と手の協調を楽しみながら育てます。 - 感覚遊び
→カラフルな動きや音で 感覚を刺激します。 - 繰り返し遊びによる集中力の育成
→ 何度も「入れる→落ちる→音が鳴る」を繰り返し、遊びながら集中力や持続力が育まれます。



小さな子でも「自分でできた!」と感じやすく、成功体験につながっていきます。
また、
- 乳幼児期:手づかみや指先の動き
- 幼児期:順序やルールを理解する力
- 発達支援:視覚・聴覚の強い刺激で興味関心が広がっていく
「次は赤の玉だね!」「チリンってなったね!」など会話が生まれ、色の理解にもつながっていきます。
スロープトイ
- 因果関係を理解する
→ 「車を置くと → 滑る → 下まで行く」(自発的な行動へ繋げる)、原因と結果を繰り返し体験できる。 - 視覚的な追視力の発達
→ 車が左右に揺れながら落ちる動きを目で追う力(追視)を育てる。 - 手先の発達と協応動作
→ 車を持ってスロープに置く動作で手指の技巧性や目と手の協応。 - 繰り返し遊びによる集中力
→ 同じ動きを何度も楽しむことで集中力・持続力を育てます。 - 色・数・順序の理
→ 車を色で分ける、順番に流すなど、色彩感覚や数の概念に触れる。



聴覚(カタカタと鳴る)・視覚(左右に揺れる動き)・触覚(車を持ち上げて置く動作)と、複数の感覚が同時に心地よく刺激されます。
はじめてのつみきRING10
- 数の基礎理解
→ ブロックやパーツを「合わせて10」にすることで、数量感覚や計算の基礎を体験的に学ぶことができます。 - 色の概念を育む
→ 赤・青・黄などの色分けされたパーツを通じて、色の認識・分類力が養われます。 - 分類・対応関係の理解
→ 「赤の3と青の7で10になる」など、色と数を関連づけて理解、「大きさ、量」を感覚的に理解できてきます。 - 遊びながら学ぶ習慣をつける
→ 「勉強」ではなく「遊び」として、自然に算数的思考が入ってきます。 - 手と目の協応
→積み木にしたり紐通しをしたり指先の技巧性も高まります。 - ルール理解
→数字のサイコロ、色のサイコロが付いているのでいろいろなゲームが楽しめます。



数の概念(10のまとまり)、色の概念(分類・組み合わせ)を
組み合わせることで、 視覚的・体感的に学べる教材です。
モンテッソーリ木の知育玩具
- 形・色の理解を促す
→ 形(丸・三角・星など)や色(赤・青・黄など)を視覚的に識別する練習になります。 - 見通しを持たせる
→ カードの並びを見て「次に何が来るか」を予測でき、順序やルールを理解する力が育ちます。 - 切り替えのサポート
→ 遊びを通じて「片付け」「次の形へ」など、自然に切り替えを経験でき、活動の移行がスムーズになります。 - 自己管理力・成功体験の積み重ね
→ 「自分で正しい形を選んで入れる」という小さな達成体験を繰り返し、自己肯定感や集中力の向上につながります。



形や色を見て選び、当てはめることで 認知力の向上・集中力アップ・切り替えのしやすさ・成功体験の積み重ね ができます。
遊びながら学べるので、自立を促すサポートにもなります。
タイムタイマー
- 時間の見える化
→ 「あとどれくらい?」が 視覚的にわかります。 - 見通しを持たせる
→ 活動や課題の終了を予測できて、不安が減ります。 - 切り替えのサポート
→ 帰りの支度や、行っている活動から次の活動へなど、スムーズに移行 できる。 - 自己管理力の育
→ 子ども自身が「時間を意識して行動する」練習になる。



不安軽減、集中力アップ、切り替えのしやすさ、自立促進、成功体験を重ねることが出来ます。
家庭でできる知育の工夫


知育おもちゃや遊びの時間はもちろん大切ですが、日常生活そのものがことばを育てる大きな場になります。
特別な教材がなくても、ちょっとした意識で日々のやり取りが言語発達を促す「知育タイム」に変わります。
日常生活の中で声かけを増やす
食事や着替え、外出準備など、生活のあらゆる場面で語りかけを意識しましょう。
「スプーンを持ってね」「靴下はどっちの足かな?」と、動作に合わせて声をかけることで、言葉と行動がリンクします。
ポイントは短く・はっきり・繰り返すこと。長い説明よりも、生活に即したシンプルな言葉の方が吸収されやすいです。
子どもの発話を待つ姿勢
つい先回りして言葉を補ってしまいがちですが、少し待つことで子どもが自分から言葉を出すきっかけになります。
例えば、コップを手渡すときに「何が飲みたい?」と聞き、答えるまで待つ。
ジェスチャーや指差しで答えた場合も、「お水がいいんだね」と言葉で返すと、モデルとしての発話を自然に聞かせられます。
成功体験を積ませる褒め方
「すごいね!」だけでなく、できた内容を具体的に褒めると自信とやる気が育ちます。
「りんごって言えたね」「最後までお話できたね」と、行動や発話を具体的に言葉にして伝えましょう。
自分の発言や行動が認められる経験は、言葉を使う意欲の向上につながります。
テレビ・タブレットとの付き合い方
映像からも新しい言葉は覚えますが、一方通行のインプットだけでは会話力は育ちにくいです。
視聴時間を決め、見終わった後に「誰が出てた?」「何してた?」と話題にすることで、アウトプットの機会に変えられます。
また、画面を見る時間が長すぎると、会話や遊びの時間が減るため、「生のやり取り」がある時間を確保することが大切です。
言葉の遅れが気になるときの相談先


言葉の発達には個人差がありますが、年齢相応の伸びが見られない、会話が続かない、発音が極端に不明瞭などのサインが続く場合は、早めに相談できる場所があります。
早期の支援は、その後の成長や自信に大きく影響します。
地域の子育て支援センターや保健センター
まず気軽に相談できるのが、自治体が運営する子育て支援センターや保健センターです。
1歳半健診や3歳児健診では、ことばの理解や発語の状況を観る機会があり、気になる点があればその場で相談できます。
必要に応じて、発達支援機関や医療機関への紹介を受けられます。
定期健診以外でも、随時相談日を設けている自治体が多いため、気になる時期に活用すると安心です。
児童発達支援事業所・放課後等デイサービス
発達がゆっくりな子や特性のある子が通い、ことば・運動・社会性などを総合的に支援する場所です。
0歳〜6歳(就学前)なら児童発達支援、小学生〜高校生なら放課後等デイサービスが対象となります。
専門スタッフ(児童発達支援管理責任者・保育士・言語聴覚士など)が、遊びや活動を通して言語発達を促す個別支援計画を立ててくれるため、家庭での関わり方のヒントも得られます。
言語聴覚士(ST)による評価と訓練
言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist)は、ことばやコミュニケーション、発音の専門家です。
病院やリハビリ施設、発達支援センターなどで、発達検査や言語評価を行い、一人ひとりに合わせた支援やアドバイスをしてくれます。
発音の改善、語彙の拡大、会話の組み立てなど、具体的な課題に合わせた支援が受けられます。
医療機関での発達相談
小児科や小児神経科、発達外来では、ことばの遅れを含む発達の全体像を確認できます。
必要に応じて脳や聴覚の検査を行い、医学的な要因がないかを調べます。また、診断がついた場合は、公的支援や療育の利用につながりやすくなります。
「相談するほどではないかも…」と思っても、気軽に受診して構いません。早期に状況を把握することが、適切な支援の第一歩です。
まとめ┃悩んだときは近くの施設へご相談ください
言葉の発達は、子ども一人ひとりのペースや個性によって大きく異なります。
「話し始めるのが遅い」「会話が続かない」といったサインがあっても、遊びや日常生活の中での関わり方によって、少しずつ伸びていくことは珍しくありません。
今回紹介したように、
・月齢や発達段階に合わせた遊びや知育おもちゃ
・日常の中での声かけや発話を促す工夫
・専門機関や支援サービスの活用
を組み合わせることで、家庭でも無理なく言葉の発達をサポートできます。
もし不安や迷いがあるときは、早めに地域の支援センターや発達相談機関に相談してみましょう。
専門家と連携しながら、家庭での取り組みを続けることが、子どもにとっての安心感と自信につながります。
ことばは、世界を広げる大切な道具です。日々の関わりを通して、「話すって楽しい!」という気持ちを育ててあげることが、子どもの可能性を伸ばしていきます。
私がいるぽかぽかステップこ・と・ばでは、ことば特化型の児童発達支援・放課後等デイサービスとして、ことばに難しさを抱えるお子様に支援を行っております。
体験・見学は下記のフォームからお申し込みください!