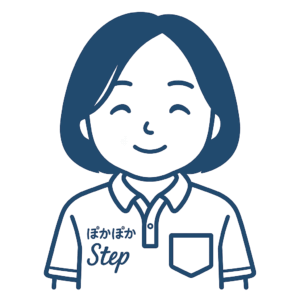ぽかぽかステップこ・と・ばの鈴木です。
お子さんの日常生活における「困りごと」について、私たちがどのように寄り添い、支援しているのかを数回に分けてお伝えしていきます。
「生活の自立」って、実はとても複雑なこと
「トイレに間に合わない」「着替えに時間がかかる」「食事中に席を立ってしまう」―保護者の方からよくこんなお悩みをうかがいます。
一見シンプルに見える日常の動作も、実は多くのステップで成り立っています。たとえば手洗い一つとっても、「水栓をひねる」「石鹸を泡立てる」「指の間まで洗う」「すすぐ」「タオルで拭く」という複数の工程があり、それぞれに注意を向ける必要があります。
発達に特性のあるお子さんにとって、これらの一連の流れを理解し、実行することは想像以上に高いハードルなのです。
「できない」のではなく「やり方を知らない」
私たちは、お子さんの行動を「できない」とは捉えません。
「まだやり方を知らない」「どうすればいいか分からない」状態だと考えています。
たとえば、トイレに間に合わないお子さんの場合、尿意に気づくタイミングが遅れていたり、トイレまでの段取りが分からなかったり、衣服の着脱に時間がかかったりと、さまざまな要因が重なっていることがあります。
食事のマナーについても同様です。遊び食べをするお子さんは、食事に集中するのが、まだ難しかったり、「食べる」という行為よりも周りの刺激が気になってしまったりしているのかもしれません。偏食が強いお子さんも、味覚や触覚の過敏さがあったり、初めてのものへの不安が強かったりするだけで、決して「わがまま」ではありません。
見えにくい「清潔」と「時間」の概念
特に難しいのが、「清潔」や「時間」といった目に見えない概念です。
爪が伸びていることや、顔に汚れがついていることは、大人には気になりますが、お子さん本人は困っていないことがあります。「汚れている」「不快だ」という感覚そのものが育っていない場合もあるのです。
また、生活リズムの安定も大きな課題です。「朝7時に起きる」「夜9時に寝る」といった時間の概念は抽象的で、特に時計が読めない段階では理解が難しいものです。お腹が空いていないのに「お昼だから食べなさい」と言われても、なぜ今食べなければいけないのか納得できないお子さんもいます。
持ち物管理は「記憶」と「段取り」の複合技
「明日の準備ができない」「ランドセルの中がぐちゃぐちゃ」といったお悩みもよく聞きます。
持ち物を管理するには、「何が必要か知っている」「それがどこにあるか把握している」「取り出す順序を考える」「元の場所に戻す」など、実に多くのスキルが必要です。これらは記憶力、空間認識、実行機能など、複数の脳の働きを同時に使う高度な作業なのです。
着替えも同じです。「どの服をどの順番で着るか」「脱いだ服はどこに置くか」「裏返しになっていないか」など、一つひとつの判断の連続です。朝の忙しい時間に、これらすべてをスムーズにこなすのは、発達段階によっては大変なチャレンジです。
体の声に気づき、言葉にする力
「おなかが痛い」「疲れた」「眠い」―自分の体調や気持ちを言葉で伝えることも、立派な自立のステップです。
しかし、体の感覚を正確に認識し、それを適切な言葉で表現することは、決して当たり前のことではありません。体調不良をうまく伝えられず、突然泣き出したり、イライラして物に当たったりすることもあります。
自分の状態に気づき、それを表現する力は、安全で健康な生活を送る上で欠かせません。体のサインを見逃さず、適切に助けを求められることが、将来の自立にもつながっていきます。
小さな成功体験の積み重ねが、自信につながる
「ぽかぽかステップこ・と・ば」では、一人ひとりの特性や発達段階に合わせて、具体的で分かりやすい支援を行っています。
視覚的な手順表を使ったり、実際に一緒に練習したり、できたときにはしっかり認めて褒めたり。焦らず、お子さんのペースで「できた!」という体験を重ねていくことを大切にしています。
生活の自立は、一日で達成できるものではありません。でも、毎日の小さな積み重ねが、やがて大きな自信となり、お子さんの未来を支える力になっていきます。
お子さんの日常生活での「困った」が、少しずつ「できた!」に変わっていく―そんな瞬間に立ち会えることが、私たちの喜びです。
この連載を通じて、保護者の皆さまにも新しい視点や安心をお届けできればと思います。
どうぞお付き合いください。